第66回 新自由主義(ネオリベラリズム)が抱える本質的な欠陥
『ボーイング 強欲の代償 −連続墜落事故の闇を追う−』(江渕 崇 著、新潮社)
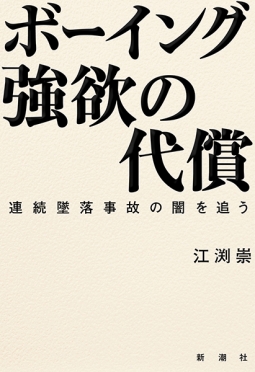 ここ数年、エクセレントカンパニーであったはずの米ボーイング社が、文字通りぐちゃぐちゃになっている。
ここ数年、エクセレントカンパニーであったはずの米ボーイング社が、文字通りぐちゃぐちゃになっている。
次世代小型旅客機の目玉であった「737MAX」は2017年から航空会社への機体引き渡しが始まったが、2018年10月にはジャカルタで、2019年3月にはアディスアベバで墜落事故を起こし、共に乗客乗員の全員が死亡した。737MAXは全世界的に飛行停止処置になり、事故調査の過程でそもそも機体設計に問題があったことが判明した。
運行再開後の2024年1月にはアラスカ航空が運用する737MAXで、不要のドアをふさぐドアプラグという部品が離陸直後に吹き飛ぶ事故が発生。また、同年2月にはユナイテッド航空の737MAXで、着陸時にラダー(方向舵)が動かなくなる故障が発生し、米国家運輸安全委員会が、重大な不具合の可能性があるとして「緊急安全勧告」を出した。
宇宙分野でも、新しい有人宇宙船「スターライナー」が、2019年12月の無人飛行試験でトラブルが発生して搭載推進剤を浪費してしまい、予定していた国際宇宙ステーション(ISS)とのドッキングを中止して帰還した。続く2022年5月の無人飛行試験は成功したが、2024年6月の初の有人飛行試験では、ISSへのドッキングに成功したものの、ヘリウム漏れやスラスターのトラブルを起こして、機体は無人で同年9月に帰還させた。宇宙飛行士2名はISSに残留し、この原稿を書いている2025年2月初めの時点で、まだ地上に帰還できないでいる。
また、米主導の国際協力による有人月着陸計画「アルテミス」で、ボーイングが担当する宇宙飛行士打ち上げ用超大型ロケット「SLS」は、当初2018年に最初の打ち上げを行う予定が、ずるずると4年も遅れて2022年11月に最初の打ち上げに成功した。が、2号機の打ち上げは2021年予定が2023年に遅れ、2024年となり、現在では2025年9月を予定している。その間にSLS開発経費はとめどもなく膨れ上がり、2024年までに、260億ドル(約4兆円)超が費やされている。
ボーイングの収益のもう一つの柱である軍用機部門でも、KC-46空中給油機が、2024年8月に相次いで空中給油用パイプを機体内に引き込むことができなくなるトラブルを起こした。KC-46は空中給油システムをすべてデジタル化した上で自動化したが、このシステムは以前からトラブルが頻発しており、問題となっていた。
一体ボーイングになにが起きているのか──本書はボーイングの失敗を追うことで、単にボーイングが内部に抱える問題のみならず、アメリカ資本主義が抱える問題、さらには1980年代以降の世界を席巻してきた新自由主義(ネオリベラリズム)が抱える本質的な欠陥にまで降りていく。タイトルにある「強欲」とは「企業は収益を上げて株主に配当を出すことこそが正義」とする新自由主義を意味する。著者は朝日新聞経済部デスク。アメリカ駐在時からボーイングの問題を集中的に取材した経歴を持つ。
本書から最初に見えてくるのは、「よいものを作って社会に貢献する」という意志で創業され、その意志を体現した製品で成長したボーイングが、社内にネオリベラリストたちに食い込まれ、「ものつくり」を第一とする文化を破壊されて、高配当と共にトラブルの泥沼に落ちていく姿である。
始まりは1980年代のレーガン政権と米ソ冷戦の終結だった。レーガン政権は「社会を合理化し、無駄を省いて高収益を上げることこそが正義」という新自由主義的政策を推進した。また、冷戦終結とそれに続くソ連崩壊は、米軍事費削減を招き、結果として軍関係の官需の大きかった米航空宇宙産業は、大規模な業界再編成の時代へと突入していく。
業界の大変動にあたって、ボーイングはヒューズ社の衛星部門を買収するなどして拡大路線を採用した。その中でじわじわと、ネオリベラリズムが社内に忍び込んでくる。「高品質の製品をカスタマーに向けて送り出す。そのためにはどれだけコストがかかっても構わない」という社風に、コスト意識が入り込み、人も開発予算も徐々に削られるようになる。
買収による拡大路線の結果、1997年にボーイングは経営が行き詰まっていた航空宇宙大手のマクダネル・ダグラス(MD)社を買収・合併する。MD社はかつては革新的な旅客機「DC-3」「DC-8」などを開発した民間航空機大手だったが、3発大型旅客機「DC-10」が起こした事故で経営が傾き始め、さらに後継の「MD-11」旅客機の開発に失敗し、民間機部門でボーイングに大きく出遅れた。その背景には、MD社経営陣が一足先にネオリベラリズムに染まり、株価優先でエンジニアリング軽視の経営を行ったことがあった。
が、他方でMD社はF-15戦闘機をはじめとした手堅い官需でシェアを取っていた。そこが官需が欲しいボーイングにとって魅力だった。
この買収・合併は、ボーイングにとって「トロイの木馬」だった。合併したMD社から来た経営幹部が、ネオリベラリズムの収益第一主義を大々的にボーイングに持ち込んだのだ。MD社幹部にとっては「会社を高くボーイングに売る」という点で大成功だった。ボーイングに入り込んだ元MD社幹部たちは、やりたい放題を始める。結果、合併は「羊によるオオカミの買収」と呼ばれるようになった。
新しいボーイングの経営幹部は、「そんなことをやっていては非効率で収益が上がらない」と開発と製造の現場を敵視した。現場は反発するが、経営側は「経営改革」と称してじりじりと押していく。
無駄を省け。大切なのは収益を上げることであって、高品質の製品を世に送り出すことではない。高品位を実現するために、無駄ガネなんか使うな。無駄な人員を雇うな。品質が低かろうと、売れて収益が上がればそれでいい──。そんな経営側を正当化する論理を裏打ちしたのは、レーガン政権以降、世界を席巻した「収益を上げることこそ善」のネオリベラリズムだった。
やる気のある技術者はボーイングを去るようになり、イエスマンばかりが後に残って昇進するようになる。その一方で、ボーイング経営陣は株主には高配当を出して自らの業績として誇り、高収益を理由に自らにはお手盛りの巨額の給与(報酬)を出すようになった。
「良いものを作り、世に送り出す」という一点で団結し、家族主義的に運営されてきた開発と製造の現場は、最初はゆっくりと、やがて雪崩のように崩壊していった。後に残ったのは、誰も責任を取らない無責任な現場だ。経営幹部が責任を取らないのだから当然そうなる。
その中でボーイング幹部は、新型機「787」の製造のために、世界的なサプライチェーン網の編成に着手する。サプライチェーンといえば聞こえは良いが、つまりは世界中から技術を持つ下請けをかき集めて組織化するということだ。自分でゼロから技術を開発するよりも、すでに技術を持っているところから買ってきたほうが安くあがる。世界中から選りすぐりの最高の技術を持つ会社を選んで部品を作らせ、その部品を最終的にボーイングに集めて組み立てるだけにすれば、無駄は省け、ますます高性能の機体を安く製造することができ、一層の収益が得られるだろう。
が、そううまく話は進まない。技術が空洞化したボーイングの開発現場は、機体コンポーネントの開発までをも下請けに丸投げすることになる。集まったコンポーネントをボーイングがうまくまとめ上げられるならばいいが、全体システムをまとめ上げる技術力もまた、「収益至上」の方針のために弱体化してしまっている。結果、「787」の開発は遅れに遅れ、開発コストはかさみ、就航後も新型のリチウムイオンバッテリーが出火するというトラブルを起こすことになった。
ネオリベラリズムの収益第一主義の経営は、単にボーイングというエクセレントカンパニーを蝕み、腐敗させていくだけではなかった。同時に、航空機の安全を担保するための政府の仕組みにも食い込んで、腐敗させていった。ボーイングは航空機設計の安全を監視する連邦航空局(FAA)と癒着するようになり、さらには資金力を駆使して政治に働きかけることによるFAAの弱体化も進行させた。FAAの監視は徐々に骨抜きにされ、ボーイングの働きかけを受けた政府はFAAの権限を削っていく。ここでも「規制を緩和して民間企業が自由に動けるようにすることで、経済活動を効率化して一層の収益を上げられるようにする。その結果として経済を成長させる」というネオリベラリズムの論理が大義名分として使われた。
これらのことが20年あまりにわたって進行し、結果発生したのが、737MAXの連続墜落事故だったのだ。「737」は1965年開発開始、1967年初飛行という古い機体で、2回の大改修を受けて近代化され、世界中の空を飛び続ける近距離旅客機だった。が、その設計は限界に達しており、本来ならボーイングはゼロから新しい新世代の近距離旅客機を開発すべきだった。しかし、ゼロからの機体開発はコストがかさむ。FAAの形式認定を受けるためにも、既存機の改修よりも遙かに手間と時間がかかる。また、カスタマーである航空会社としても、新型機の場合は新たにパイロットに機種転換の訓練を受けさせて、運航人材を育成する必要があるが、既存機の改修だとそのための手間が小さくなる。その結果、ボーイングは737に3回目の大改修を施して、737MAXを開発することにした。
ところが、737の基本設計は、現代の直径が大きなターボファンエンジンを翼の下に搭載するには、着陸脚が短すぎた。地面からエンジンまでのクリアランスを確保しつつ大直径ターボファンエンジンを搭載するため、エンジンの取り付け位置は前進し、主翼から前方に大きく突き出ることとなった。が、前に大きく突き出たエンジンは、機体が大きな迎え角を取った時に、空力的に機体を不安定にする。ボーイングは、大きすぎる迎え角を取った場合に、電子制御で強制的に下げ舵をとって機首を下げる機構を加えることで、不安定にならないようにした。
この仕組みに問題があり、機体を降下させてはならない状況下で、強制的に機首を下げてしまい、墜落事故を引き起こしたのである。
本書が描いていくのは、単にボーイング一社が腐敗・凋落していくプロセスだけではない。ボーイングの腐敗の背後からは、アメリカ社会の腐敗と堕落が立ち上がってくる。事はボーイング一社ではなく、アメリカという国全体を覆う問題なのだ。
そして腐敗と堕落にお墨付きを与え、推進していく思想として、新自由主義=ネオリベラリズムの存在が徐々に見えてくる。ネオリベラリズムは、1980年代に米レーガン政権が政策の中心に据え、英サッチャー政権が推進し、日本には中曽根政権が持ち込んだ。
新自由主義=ネオリベラリズムは、徹底して市場原理を重視する経済思想だ。政府による経済への介入を最小限に留め、民間が主体となって経済を形成していくべきだとする。市場原理に基づき、民間は効率的に動く。効率的に動けば、それだけ経済は強くなり、成長すると主張する。効率を測る指標は、市場だ。効率良く動けば、それを市場が高い価値があると評価する。より効率的に動く者が経済的な勝者となるので、時と共に経済も社会も強靱で効率的なものになる──。
市場による評価とは、価格だ。つまり新自由主義は、社会に存在する価値をその時々の金額の多寡に還元する。
ここに新自由主義=ネオリベラリズムの陥穽があった。この社会は必ずしも金銭の多寡では評価できない価値がある。それは「よいものを作る」という意志と、その意志を体現する共同体の存在であったり、短期に儲けを出すよりも長期の安全を優先する思想であったり、すぐには収益を生まない社会インフラを長期的に整備していくことで人々がより暮らしよくなるようにする知恵である。
そういう「社会の中に蓄積され、長期的に人類社会を進歩させる叡智」というべきものを、新自由主義=ネオリベラリズムはあっさりと切り捨ててしまった。人々は短期の利益に惑わされ、「企業収支のV字回復」のような目先の成果に歓声を送り、「規制緩和」の美名の元に必要な社会システムを破壊して猛悪なる資本の野放し状態を現出させ、結果として社会を破壊してしまったのである。
その意味では、新自由主義=ネオリベラリズムは、20世紀前半のファシズムと対応する、「20世紀後半から21世紀にかけてのファシズム相当思想」と形容すべき、途方もない危険思想と言わねばならない。
新自由主義=ネオリベラリズムの破壊の最先端に、今、アメリカで成立してしまったトランプ政権がある。中曽根政権以来の新自由主義=ネオリベラリズム路線の上に、日本の石破政権もあるわけで、アメリカの状況は日本にとっては他人事ではない。一刻も早く、この悪しき思想の影響を社会から払拭しなくてはいけない。短期的なカネとは違う、別の長期的ですべての人を幸せにするような経済に対する物差しを取り戻さなくてはいけない。
ボーイングの凋落はまったく他人事ではない。気がつけばこの20年ほどで、ボーイングと同じプロセスを経て凋落し、退場していった日本の大企業も散見されるではないか。
2025年初頭の今、必読の書である。
【今回ご紹介した書籍】
●『ボーイング 強欲の代償 −連続墜落事故の闇を追う−』
江渕 崇 著/四六判変型/320頁/定価2420円(税込み)/2024年12月発行/
新潮社/ISBN 978-4-10-355981-8 C0034
https://www.shinchosha.co.jp/book/355981/
※電子書籍もあります。
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2025
Shokabo-News No. 402(2025-2)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター。1962年東京都出身。現在、日経ビジネスオンラインにて「チガサキから世間を眺めて」を連載の他、「Modern Times」「Viwes」「テクノトレンド」などに不定期出稿中。近著に『母さん、ごめん。2──50代独身男の介護奮闘記 グループホーム編』(日経BP社)がある。その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数。
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は、裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月に連載しています。Webサイトにはメールマガジン配信後になるべく早い時期に掲載する予定です。是非メールマガジンにご登録ください。
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 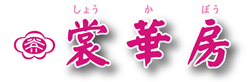
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム