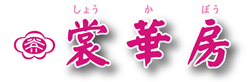 |
|
|
||||
雑誌「生物の科学 遺伝」 2001年7月号
●特集 検証・20世紀の生物科学●
はじめに
浅島 誠
この21世紀の初めにあたって,20世紀の生物科学を検証することは,21世紀を展望するためにも必要なことであると思われる.20世紀という100年の間に起こった生物科学の発展をみると,19世紀までの約1900年間 で生じたり得られたりした知識と対等となるぐらいの大きな変化や成果がみられたと言っても過言ではない.しかしながら,それらの発展も19世紀までの生物科学の礎があったればこそである.例えば,メンデルの遺伝の法則の発見(1865),パスツールによる酪酸発酵が嫌気性細菌によるという知見(1871),ルーによるカエル卵への初めての胚手術と実験発生学の創始(1881),ゴルジによる銀染色法による神経繊維の形態学的研究(1885),カヤールのニューロン説(1888),アルトマンによる核酸の命名(1889),エールリッヒによる免疫学の研究(1892)など数多くの基礎的研究が芽生えていた.しかしながら全体としてみると,19世紀までは生物の現象の観察,比較形態学的研究や免疫学や核酸,酵素などの概念がでてきてはいたが,その本体や本質については未だつかめていなかった.そのような中で19世紀の最後の年の1900年,コリンズらによってメンデルの法則の再発見が行われ,20世紀の遺伝学への扉が開かれたように思われる.
20世紀の自然科学をふりかえれば,前半は物理学と化学が主流であったが,後半はむしろ生物科学が大きな役割を占めるようになった.遺伝学もメンデルの法則から遺伝物質が染色体にあることがまず明らかになった.そして遺伝物質の突然変異,性の決定,集団遺伝学の研究,肺炎菌の形換因子がDNAであることを証明したアベリーら(1944)の研究はその後のDNA研究の基礎をなすものである.それは1953年のワトソンとクリックのDNAの二重らせん構造の解明(1953)へとつながっていく.このワトソンらの研究が生物科学の大転換期といえよう.
DNAやRNA等の核酸の研究技術は年と共に改良され,20世紀末にはヒトも含めたその種がもつ全遺伝子のゲノムそのものをすべて読みとるところまで進んだのである.地球上には800万種以上の生物がいると言われているが,そのうちの約40種の全ゲノムの解読が終わったことは,10年前までは考えられなかった生物科学の一大イベントであるといえる.アメリカのクリントン大統領は,「ヒトの全ゲノムの解読は生物科学の一大モニュメント的成果であり,それは人類が初めて月に着陸したことと同じである」と述べた.このことも,生物科学の20世紀末の成果はその社会的意義が大きいことを示している.そして,20世紀末にはすでにこれらの成果を踏まえて,21世紀にむけてポストゲノムの方向へと研究が進んでいる.このように,DNAの分析と解読を中心にした分子遺伝学の進歩は,生命に対する私たちの認識,概念,考え方を大きく変えたといえよう.また,種々の酵素や筋肉などの機能をもつタンパク質や糖の研究の流れも20世紀の大きな成果である.1917年,ホプキンスは筋肉において解糖を発見した.タンパク質としてインスリンは1920年に分離されたが,その後,結晶化に7年がかかり,インスリンのアミノ酸の配列が決まったのは1953年サンガーによってであった.約33年の歳月がかかったことになる.しかしながら,サンガーが開発したアミノ酸配列の決定法はその後のタンパク質科学に大きく寄与した.タンパク質の構造と機能の解析,生体内の種々の代謝回路の解明,細胞内情報伝達のしくみの解明の詳細は本シリーズの中で述べられる予定である.
一方,発生学に目を転じると,19世紀の後半ルーによって創設された実験発生学が20世紀の初頭に大きく発展し,シュペーマンらの形成体(オーガナイザー)の発見(1918)やフォークトの原基分布図の作成(1925)などがなされた.とくにシュペーマンらの形成体の発見はその後の発生学のメインテーマとして取りあげられ,その本体を探し出す研究はその後約60年間続けられてきて,近年になって少しずつ分子の言葉で語ることができるようになってきている.フォークトの原基分布図の研究はその後,細胞系譜の研究となって続いている.このあたりやホメオボックス遺伝子などについての詳細は特集記事に譲りたい.しかしながら,発生過程における遺伝子間の比較がなされ,分子発生進化学や進化学も再び論じられるようになってきた.進化学はともすればその証明が非常に難しいとされてきたが,各生物種のもつDNAの配列の中にその種のもつ歴史が見つかってきたのである.このように進化学の中で改めてわれわれヒトの歩いてきた道である“ヒトの起源と他の生物との関係”も問い直されるようになってきた.また,細胞についても分子生物学的研究が進んだ.細胞間相互作用に関係しているような細胞間基質,細胞接着分子等も明らかになってきて,多細胞の構築になくてはならないものとして理解されるようになってきている.またミトコンドリアDNAを中心とした細胞内共生説は,生命や細胞がどのようにしてできたのかという起源の問題に迫る細胞内共生という現象と共に,進化学に新しい概念を巻き起こした.
一方,ヒトの病気やそれに関連した研究も大いに進んできた.がんの研究や免疫学,神経科学の研究など,各分野でその本体をつかまえるところまできた.がん研究についてはウイルス説や発がん物質説,放射線などさまざまな角度から研究され,いかにして正常細胞をがん化していくのかの仕組みについても明らかになってきている.ウイルス説をとったラウスはニワトリの肉腫から発がんウイルスを発見(1911)したし,発がん物質では山極勝三郎がウサギの耳にコールタールを塗って正常細胞を人工的にがん化させることに成功した.そして現在ではがん関連遺伝子が多数見つかり,それらはヒトの遺伝子の中にも同じ配列があることもわかってきた.がんの研究は,古くて新しい重要なテーマとして今も研究されている.また,免疫に関する研究は19世紀の後半メチェニコフやエールリッヒによって始まったが,メダワールによる移植免疫の研究に端を発して(1953)免疫生物学は飛躍的に発展する.免疫グロブリンIgGの全一時構造がエーデルマンらによって決定され,その後,利根川らにより免疫グロブリンの遺伝子の再配列の仕組みがわかってくると,生物の多様性と適応を分子レベルで理解することが可能になった.
このほか生理学や内分泌学でもつぎつぎに新しい現象や概念が発見され,分子レベルでの解明によってこれらを分子の言葉で語れるようになってきた.このようにしてみると,20世紀の生物科学は,従来の現象の記載をこえて,生物のもつさまざまな現象を分子の言葉(それはまた物理と化学の言葉と言い換えることもできる)で明らかにしてきたと言える.そのことによってその現象そのものを引きおこす本体が明らかになってきてもいる.他方,20世紀末から21世紀に向かって,地球上の生態系の破壊の問題,また新しい技術による種speciesの概念の変化,生殖技術の発達,遺伝子操作,人工臓器,クローン生物など,さまざまな技術がそれまでの生命観を大きくかえる出来事や事実が明らかになり,再び“生命”“人間の尊厳”などが問い直されてもいる.これらは私たちヒトの存在に直接的または間接的にかかわる重要な問題であり,また社会的コンセンサスが必要となる研究もでてきた.これらをどのように整理し論議していくかは,今後のヒトのあり方を含め大切になってきている.そのような中で生物科学は,生物全体の多様性や自然との調和など,重要でかつ緊急の多くの問題を抱え込むことになっている.人間社会中心の思想からだけでなく,地球規模で自然や他の生物との共存がいかに重要であるかを再認識すると共に,新しい“生命哲学”が必要である.
20世紀を終え,21世紀を展望するとき,遺伝子操作や生殖革命,クローン生物など,今までヒトが経験したことのない技術を用いた生活の便利さや目先の効能ばかりに目を奪われて,地球上の多くの生物種species のもつ歴史や多様性,生態系を通しての自然との調和などをないがしろにすることは許されない.これらの問題にどう取り組んでいくかが問われているのである.20世紀の生物科学を検証するもう一つの重要な意味がここにもある.(あさしま まこと,東京大学大学院 総合文化研究科)
「検証・20世紀の生物科学」は次号以降もシリーズとして続きます(3月号〜11月号の予定).ラインナップは以下の通りです.
神経系の情報伝達−シナプスの世紀(高垣玄吉郎)
比較行動学から行動生物学へ(青木 清)
免疫学(奥田研爾・浜島健治)
がん研究(石川隆俊)
生物生産物質(山口彦之)
分子生物学−核酸研究(廣川秀夫)
分子生物学−タンパク質研究(西村善文)
細胞周期・細胞分裂・細胞運動(岸本健雄・沼田 治)
タンパク質合成と輸送・オルガネラの機能(田代 裕・山本章嗣)
光合成の研究(宮地重遠)
進化学(三中信宏)
分類学から多様性の生物学へ(岩槻邦男)
生態学と地球環境(嶋田正和)
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.