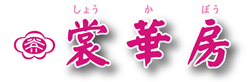 |
|
|
||||
特集 I 動物行動学の展望
特集にあたって
桑村哲生動物行動学=Ethology(エソロジー)と呼ばれる分野が成立したのは20世紀半ばのことである.
その際,とりわけ重要な役割を果たしたのは, 1973年にノーベル生理学医学賞を受賞した,ローレンツ,ティンバーゲン,フリッシュという3人のヨーロッパの学者たちであった.フリッシュ(Karl von Frisch)はミツバチの「8の字ダンス」で有名だが,動物の感覚とコミュニケーションの研究を実験的手法により発展させた.
これに対してローレンツ(Konrad Lorenz)は鋭い観察眼と洞察力のもち主で,たとえば『ソロモンの指環』(原書初版1949年)には行動観察のおもしろさが生き生きと描かれている.一般には「刷り込み」で有名かもしれないが,生得的解発機構,社会行動,種間比較による系統論など幅広い研究によりエソロジーの枠組みを作りあげた.ティンバーゲン(Niko Tinbergen)はトゲウオの攻撃行動や求愛ジグザグダンスの研究で知られているが,むしろ巧妙な野外実験が得意であった.
彼は『本能の研究』(原書初版1951年)の序論において,のちに「ティンバーゲンの四つの問い」と呼ばれることになる動物行動学のアプローチについて述べている.すなわち,「動物はなぜそのように行動するのか?」という問いに対して,
1)刺激−反応の因果関係(生理的メカニズム),
2)行動の個体発生,
3)進化の歴史(系統発生),
4)行動の目的・機能(生存価・適応的意義)
の四つの側面から答える必要があることを指摘した.前者二つを合わせて至近要因(How questions=どのようにして?),後者二つをまとめて究極要因(Why questions=なぜ?)ともいうが,動物行動学はその両面から行動を理解しようとする分野である.日本においては1970年前後にローレンツなどの著作が多数翻訳出版されるようになり,動物行動学が普及し始めた.いっぽう,1970年代半ばから世界の動物行動学は大きく変貌する.
一つは脳・神経生理学の発展により, Neuro-ethology(神経行動学)と呼ばれる分野が独立し始めたことである.ニューロエソロジーの歴史については,本特集の中の一つ(池渕)で紹介されているのでここでは省略する.
もう一つは,行動生態学Behavioral Ecology(あるいは社会生物学Sociobiology)と呼ばれる分野の発展である.その特徴は,集団遺伝学と分子遺伝学の成果を踏まえて洗練されたダーウィン進化論(自然選択説)を基礎において,行動の機能と進化を説明しようとする点にある.
行動の進化はそれまでもさかんに論じられていたが,ローレンツなどが種(集団)全体にとっての利益(種族繁栄)を基準にして説明したのに対して,ウィルソンの『社会生物学』(原書初版1975年)やドーキンスの『利己的な遺伝子』(原書初版1976年)は,個体の適応度(子孫の数),あるいはある性質を支配する遺伝子のコピー数を基準にして説明しなければならないことを強調した.
そして,1981年にクレブスとデイビスが『行動生態学入門』という教科書を著して,この分野が急速に発展・普及していった.ちょうどそのころ,日本においては日高敏隆(京都大学教授:当時)が中心になって日本動物行動学会が設立された.
1982年に会員数約400名でスタートしたが,10年目の1991年には国際動物行動学会議(IEC:International Ethological Conference)を京都に誘致して若手研究者に大きな刺激を与え,会員数も倍増した.そして昨2001年には20周年記念シンポジウム「動物行動学の展望」が開催された.
このシンポジウムは,前年大会の公開講演会「動物行動学の過去・現在・未来:ティンバーゲンの4つの問いを問い直す」で示された問題提起を引き継ぎつつ,さまざまな分野の若手を中心に「動物行動学の展望」を自由に語り合おうという趣旨で開催された.
本特集は,このシンポジウムの演者・コメンテーターのうち一部の方にお願いして執筆していただいたものである.この特集では以下の順序に再構成してみた.
まず(1)感覚生理メカニズムの解明の例として,チョウの色覚と視細胞の構造と感度に関する研究の発展を紹介する(蟻川謙太郎).
つぎに,(2)ニューロエソロジーと分子生物学的手法の発展をふまえて,小鳥の歌行動の機能と進化を脳内遺伝子発現領域から解明していく研究(池渕万季)と,(3)ノネコの交尾行動の野外観察に,遺伝マーカー(マイクロサテライトDNA)を利用して血縁関係を調べるという手法を取り入れて,近親交配を避けていることを明らかにした研究(石田泰子)の紹介を通して,さまざまな手法を組み合わせた総合的アプローチの可能性を展望する.
続いて,(4)行動の進化を説明する戦略モデルと量的遺伝学モデルのアプローチの仕方の違いと,種間比較により行動の進化史を解明する手法を解説しつつ,行動生態学の未来を展望する(工藤慎一).
そして最後に,(5)行動生態学の発展と心理学における認知革命を踏まえて,「進化した心理メカニズム」という枠組みを紹介し,進化的人間行動研究の新たな可能性を展望する(平石 界).なお,記念シンポジウムでは「動物実験の倫理」(藤平篤志)という講演もしていただいたが,本号ではこの特集から独立させて一般解説記事として掲載されている.合わせてお読みいただきたい.
(くわむら てつお,中京大学 教養部)
特集 II 進化とゲーム
特集にあたって
巌佐 庸生物はうまくつくられている.厳しい自然の中で,効率よく餌を探し,配偶者を見つけ,子どもを残す.生物の体のしくみや生活を知るとき,誰しもこのような感想をもつ.
この生物の適応の姿をとらえるための方法が,「進化的に安定な戦略」と呼ばれるコンセプトである.2001年の京都賞基礎科学部門を受賞したジョン・メイナードスミスが提唱した.それは,現在みられる生物のさまざまな生き方は長い進化の結果なのだから,自然淘汰のはたらきを考えればどのようなふるまいが採られるかわかる,という考えに基づいている.
たとえば動物が喧嘩をすることがある.そのとき,うなり声を出す,顔を真っ赤にする,体をふくらませるといったディスプレイを行うことによって,体の直接のぶつかり合いを何とか避けようとする.またオオカミなどの捕食者では大きなシカを倒すだけの牙をもっているにもかかわらず,その武器を同種との戦いでは使わないで決着させようとする.どうしてこのような「儀式的闘争」が起こるのだろう.それは相手を殺すといういわばタカ派的なやり方は自分が殺される可能性も高く,ハト派戦略のほうが自分が傷つかなくて着実に子孫を残せるからだという.
このアイデアを,メイナードスミスは,個々の個体にとっての利益とリスク,そしてそれらが集団の性質を変化させる進化を考察して,タカ・ハトゲームと呼ばれるモデルとして定式化した(1973).大事な点は,生物たちにとって,ある挙動が有利か不利かが他の個体の挙動によって変わることだ.タカ派はハト派に対しては有利だが相手もタカ派だと怪我をするのでむしろ不利になる.このような状況を考える数学モデルは,「ゲーム」という.もともとは社会科学を基礎づけるものとして発達した.
数々のゲームモデルによって,それ以前の進化生物学では説明ができなかった多くの問題が解決できた.たとえば,動物の親が子どもを世話をする場合に,淡水魚のいくつかでみられるようにオスだけが世話をするもの,多くの哺(ほ)乳類のようにメスだけが世話をするもの,それとも鳥類の多くがそうであるように両親ともが世話するものといった多様なパターンがみられる.雌雄のそれぞれが自らにとって最大数の子どもを残せるように挙動を選ぶとするゲームは,それぞれが進化する状況を端的に表現できる(1977).
もう一つの例に性表現がある.たとえば,多くの動物のように精子生産に専門化したオスの個体と卵の生産に専門化したメスの個体とに分かれている状況と,多くの植物のように1個体が雌雄の機能を両方もつ雌雄同体との,どちらに進化するか.これについてもゲームが非常な成功をおさめた.
ハミルトンは,血縁個体の協力行動が進化しやすいことから適応の基準は個体ではなく遺伝子であることを明らかにした.これとメーナードスミスのゲーム理論とが基礎になって,生態学や動物行動学はすっかり様変わりした.今では,地球環境変化に対する生態系の応答を理解するにも,また熱帯多雨林での生物多様性の維持機構を知るにもゲーム理論は欠かせないものになっている.
メイナードスミスは,そのほか生物学のさまざまな問題について進化の観点から論じた.その中でも最も重要なものに性の進化がある.
繁殖は親と似た個体をつくることである.しかし子どもは親と同じではない.多くの生物では,親の遺伝子のセットは半分だけで,他の個体の遺伝子を半分と混ぜ合わされた子どもがつくられる.これを有性生殖という.
私たちは生物は有性生殖をするのが当たり前と考えがちだ.ところがメイナードスミスは,遺伝子を混ぜないで単純に母親のコピーをつくる無性生殖のほうがずっと効率が良いことを示した.有性生殖をする集団に性を捨てた無性タイプが現れるとあっというまに広がる.
実際には多くの生物で有性生殖が続いているのだから,異なる個体の間で遺伝子を混ぜ合わせることには,かなりの利益があるはずだ.メイナードスミスの著書『性の進化』(1978)以後,有性生殖がなぜ維持されるのかが進化生物学の未解決の問題と広く認識されるようになり,以来多くの研究者が取り組んでいる.
本特集では,京都賞記念ワークショップの講演者の方々にそこでのお話に基づいた解説をご執筆いただいた.最初に山村さんが動物行動でのゲームの例を,つぎに西條さんが人間社会での協力進化について研究を紹介される.ついで矢原さんが性の有利さについてのフィールド研究を,最後に小林さんが,遺伝子と細胞のレベルでの闘争と性のあり方について講演仕立ての解説に挑戦してくださった.
ワークショップでは,受賞者のメイナードスミス自身は,動物のシグナルに関する理論的研究の講演をした.
たとえば,2匹の動物が餌や縄張り,もしくはメスをめぐって闘争をするときには,うなり声・体色・行動など,さまざまなディスプレイを行い,相手に対して怒りを示す.これは闘争の意志を伝えているものと解釈される.相手の声やしぐさをみて,負けそうだと思うと実際にとっくみ合いにいたる前に引き下がる.縄張りから排除しようとするとき,直接おしのけるというのも一つのやり方だが,うなり声をあげるだけで退散してくれるならばそのほうが安上がりというわけだ.このときに声やしぐさは,闘争の意志,自分の強さを相手に情報として伝えているシグナルである.ディスプレイだけではない.オスのシカが繁殖期につける大きな枝角もオスの強さを伝えるシグナルなのだ.一方で,インドクジャクのオスはとても立派な羽をつける.これはメスに対して自分は健康状態も栄養状態も良い強いオスだということを誇示しており,メスはそれを信用して立派な尾を広げるオスだけを受け入れる.
しかしシグナルが機能するには,相手から信用されねばならない.本当に強くもないのに,立派な尾をもてばどうなるだろう.それで相手が退散してくれればずいぶん有利と思われるが,皆がそんなことをすれば信用されなくなるだろう.動物がもちいるシグナルがなぜ信用に足るものなのか?
この問いに答えるうえで,現在,動物行動学において定説とされるのは「ハンディキャップの原理」といわれる考え方である.大きな尾や立派な枝角といったシグナルをつくるには非常なコストがかかる.本当に強いオスならばそれが楽にできる.しかし弱い個体が無理をしてつくることはコストが大きすぎて引き合わない.結果として弱い個体は貧弱な尾や枝角をつくるのだという.またそうなっていなければ,そのシグナルは信用できないので使用されなくなるという.
今回のワークショップにおいて,メイナードスミスは,このハンディキャップ説に対して疑問を呈した.
ハンディキャップの原理の証拠とされているものの多くは,その例にはなっていないという.たとえば,昆虫のオスがうまくダンスを踊ってみせてそのことでメスがオスを受け入れるという場合,オスの神経行動能力を測定してすぐれたオスを選んでいるというのは本当だろう.しかしすぐれたオスでないとダンスがうまくできないというのはダンスをすることにコストがかかるからではない.神経系の能力とダンスの上手さとの間には自然な相関がある指標であり,だから信頼されているのだ.
メイナードスミスは,ハンディキャップ説の証拠といわれているものの多くが,よく考えると指標説で解釈するべきものだという.
動物のシグナルはどうして信頼できるのか,という問題については,以上の2説のほかに,1) シグナルを出す側と受け取る側のあいだに利害の対立がないため,嘘をつく必要がない.2)とりわけ知能が高くて社会性のある動物の場合には,シグナルに偽りがあると,そうした「評判」が広まり,それ以降は信頼を得ることができなくなる.3)「擬態」が示すように,動物のシグナルは必ずしも信頼できるわけではない.という可能性を考え,それぞれに当てはまる例をあげると共に,数理モデルによる解析を紹介した.
いま動物のシグナル進化について本を執筆中だということだ.
私は,80歳を越えるメイナードスミスが,世界の定説を覆す考え方を出し続けることにはすっかり舌を巻いてしまった.それ以来,これら諸説を包括する数理モデルは何だろうか,と考え続けている.
(いわさ よう,九州大学大学院 理学研究院 数理生物学)
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.