第31回 この上ない正気と理性が導き出す、最悪の狂気
片山杜秀 著『未完のファシズム』(新潮選書)

日清戦争(1894〜1895)と日露戦争(1904〜1905)を戦った明治の日本は、客観的かつ合理的に思考していた――この認識は司馬遼太郎が『坂の上の雲』を執筆したことで、一般的になった。では、その正気と理性が、なぜ40年後に戦陣訓の「生きて虜囚の辱を受けず」の一節、あるいは玉砕や特攻のような行為に見ることができる狂気へと崩れ落ちていったのか。司馬遼太郎は1939年に起きたノモンハン事件を描くことで狂気の源流へと迫ろうとして、取材を繰り返したが、ついに執筆することはできなかった。
実際、この上なく合理的で正気の戦争を戦った経験を持つ国が、たったの40年で狂気としか思えない戦争をするというのは、大変奇妙な話だ。
『未完のファシズム』この問題に迫る大変優れた論考だ。著者は、ファシズム史の研究を専攻する政治学者。一般にはむしろ、NHK-FMのクラシック音楽番組「音楽の迷宮」などで膨大な知識を独特の語り口で披露する、音楽評論家として有名だろう。音楽面でも著者の興味は、明治の洋楽の受容から始まった日本人の音楽作品に集中している。様々なコンサートやCDをプロデュースし、大澤壽人(1906〜1953)や須賀田礒太郎(1907〜1952)などの“忘れられた作曲家”を発掘し、作品を甦演するといった仕事もしている。
本書は、まず第一次世界大戦(1914〜1918)に対する当時の日本の知識人の反応から始まる。作家の小川未明(1882〜1961)は、海の向こうでかつてない大戦争が起きているということを、周囲の人々が全く実感していないことに懊悩する。一方、ジャーナリストの徳富蘇峰(1863〜1957)は、1920年になって『大戦後の世界と日本』という大著を世に問うて、大戦争によって欧米列強には強烈な競争原理が働いて発展しつつあると指摘し、日本はそこから脱落していると警告した。世界を巻き込む大規模な戦争に対して、知識人たちは何かが変化する兆しを感じ取っていたのだった。
では軍はどうだったのか。著者は、第一次世界大戦における、日本陸軍の青島要塞攻略戦に目を向ける。青島は、ドイツの租借地であり要塞化されていた。当時の日本は、日露戦争にあたって締結した日英同盟が有効だったので、イギリス・フランス・ロシアなどの連合国側として参戦し、極東の青島にあるドイツの要塞を攻撃したのである。
陸軍には、日露戦争の旅順要塞攻略戦では歩兵の突撃を繰り返し、多数の戦死者を出したことに対する反省があった。このため陸軍は、日露戦争後に要塞攻略戦を徹底的に研究して正攻法を確立していた。青島攻略戦には、研究成果の確認という側面があった。
要塞攻略の正攻法、それは物量戦だった。敵よりも多くの砲と弾丸を用意し、集中して要塞に打ち込んで機能を喪失させ、しかるのちに歩兵を送り込んで占領する。指揮官の勇気も兵士の決死の献身も必要ない。必要なのは最先端兵器を敵に優る物量で用意し、的確に輸送することだけ。近代戦の要諦そのものだ。この時点での陸軍は、驚くほどまともで正気だったのである。
青島攻略戦は、陸軍の想定通りに進行する。山東半島への上陸後、2か月もの時間を物資の輸送と兵站の整備に使い、いざ進撃を開始するとたった1週間で青島要塞を陥落させた。だが、この時、軍は正気でも国民が正気ではなかった。新聞は「慎重作戦」と揶揄し、人々は「陸軍は軟弱ドイツ軍に、突撃もせずに時間ばかりかけた」と嗤ったのである。
ここから著者は、様々な軍人が著した著書を紐解き、彼らの経歴と組み合わせていくことで、正気で正攻法の青島要塞攻略戦、および第一次世界大戦の経緯から、彼らが何を感じ、何を理解し、どのように対応しようとしたかを追跡していく。
青島攻略戦は、近代戦の要諦と言うべき物量戦で圧勝した。また、第一次大戦には多数の軍人が観戦武官として欧州の戦場に赴き、何が戦場で起きたかを視察した。彼らは一様に「これからの戦争は、国と国とが総力を挙げてぶつかる総力戦になる。しかも戦闘では、物量を用意できたほうが勝つ。すなわち経済力に勝る国が勝つことになる」という認識に到達する。まったくもって正気かつ論理的で、なにもおかしいところはない。
が、ここで軍人たちはもう一つの現実にぶつかる。日本は経済的な小国である、という事実だ。第一次世界大戦がもたらした特需によって日本は好景気となり、経済的にも成長した。が、それだけでは欧米列強やソ連に互するには全然足りない。なによりも日本は資源小国であり、戦争に必要な資源を自給できない。
その意味は明確である。戦争の勝敗が経済力で決まるようになった以上、このままいけば日本は次の戦争では必ず敗北する。
第一次世界大戦は、世界全体を巻き込む巨大な戦争だった。となれば、次の戦争はそれと同等以上の世界大戦となるかもしれない。明治維新以降、日本は10年間隔で戦争を経験してきた。このため大正から昭和にかけての軍人たちにとって「戦争のない長期的な平和が続く」可能性は、想像力の外にある。「10年かそこらのうちに、確実に次の戦争、それも世界大戦が起きるから、備えねばならない」と考える。
しかし――次の世界大戦で、日本は確実に敗北する――勝利することが仕事の軍人たちにとって耐え難いほど過酷な現実が突きつけられたのである。
次なる世界大戦で、日本は絶対に勝てない。
それでも、勝てない状況下で勝つためにはどうしたらいいか――ここから軍人たちの対応は二つに別れる。ひとつは「勝てない戦はしない」という行き方だ。彼らは日本が勝てる戦争の形式は局地戦だけであると考える。具体的にはソ連との国境紛争だ。これだけは勝つ必要があるが、その他の戦争は徹底的に回避しなくてはいけない。
局地戦を短期即決で確実に勝利するには、どうしたら良いか、軍人たちはそのヒントを、第一次世界大戦で40万人のロシア軍を15万人のドイツ軍が撃破したタンネンベルクの戦いを観戦することで得る。この戦いでは、分散したロシア軍を、集中したドイツ軍が機動力を生かして一つずつ包囲し、各個撃破した。
各個撃破――これだ。そのためには兵の士気を高く保つ必要がある。
そして、精鋭の兵を常備するための精神主義が発生する。この精神主義は、「勝てない戦はしない」という現実主義と表裏一体である。が、軍人は職業柄「勝てない」とは言えない。結果、現実主義の部分は流布することなく、精神主義だけが社会に流布し、増殖していくことになる。著者は、この流れが後に軍を二つに分かつ派閥の一方、皇道派につながっていくと指摘する。
もう一つが、「経済力がないのなら高度経済成長すればいい」という考え方だ。日本が経済成長するためには、資源のある植民地と、経済成長を達成するだけの長い平和な時間が必要である。この方向性が、皇道派に対立するもう一つの派閥、統制派となっていく。石原莞爾(1889〜1949)や板垣征四郎(1885〜1948)などが1931年に満州事変を起こした理由もここにある。石原莞爾は事変で満州国を成立させた後、少なくとも30年以上は平和を保って日本と満州国を高度経済成長させなくてはいけないと考えていた。
軍内部の皇道派と統制派の確執は、1936年の二・二六事件をきっかけに統制派の勝利で決着する。しかし、それまでに皇道派は「短期の局地戦に勝つための精神主義」を「統帥綱領」や「戦闘綱要」といった軍の基本的文書に書き込んでおり、その内容はまんま統制派に引き継がれた。その一方で、皇道派の前提であった「勝てない戦はしない」という語られざるポリシーは、引き継がれることなく消滅してしまった。
文書化された精神主義は、「勝てない戦はしない」という隠された制約条件から解放されて自律運動を始め、ついには玉砕や特攻といった無意味な死をも強いるほどに過激化していくのである。
加えて著者は、皇道派も統制派も共通の問題をはらんでいたと指摘する。軍人でありつつ、「勝てない戦争はしない」「経済成長すればいい」と政治に足を踏み込んでいたことだ。戦争が総力戦になった以上、戦争は戦争技術者である軍人の管轄ではなく、政治の管轄となる。戦争を行うのも行わないのも決めるのは政治的意志だし、総力戦を遂行するための国家総動員体制を構築するのも経済政策で国家経済を成長させるのも政治の仕事である。
かくして軍人たちの政治への介入が始まる。
さらに著者は、明治憲法が持っていた二重性が、こうした軍人たちの政治的な動きの邪魔をして、結果的に彼らの政治への介入を激化させたことを示す。
明治憲法は、天皇を中心とした中央集権的な内容だったと思われているが、実際には国内各勢力を巧妙に分断した分権的な内容だったというのだ。ただし、その分権制は、裏から「元勲」という非公式な最高権力が全体をコントロールすることを前提としていた。明治維新に関与した元勲たちは、昭和初期には、ほとんどこの世を去っていた。必死になって次なる世界大戦に向けて総力戦の体制を作ろうとする軍人たちの前には、総動員体制を作りにくい分権的な明治憲法だけが残っていたのだ。結果、軍人たちは過度に政治に関与し、様々な職を兼職し、日本を軍事国家化することで国家総動員体制を作ることになるのである。
著者は、総力戦のための国家総動員体制は、日本においては未完に終わったと指摘する。書名『未完のファシズム』の由来である。
なんという恐ろしい論考だろうか。個々の軍人たちは優秀であり理性的であり、現実がきちんと見えている。思考のステップも、一つひとつは合理的で間違いはない。ところが、ワンステップずつ現実に即して思考し、理性的に行動していくほどに、狂気の結果へと近づいていくのである。
本書を通読すると、正気から狂気がしたたり落ちるプロセスに、二つの要素が関係していることが見えてくる。一つは軍人という職業だ。彼らは「勝てません」とは言えない。いかに絶望的な状況であっても「勝てない」とは言えないため、彼らは勝つ方策を求め、その中から極度の精神主義が発生した。
もう一つは、日本社会における建て前と本音の乖離だ。精神主義は「勝てない戦はしない」という本音から導出されるが、本音は隠され、建前である精神主義のみが流布し、増殖していく。明治憲法の、分権体制を元勲という“本音”がコントロールする構造も同様だろう。
よくよく考えると、そもそも「軍人が“勝てない”とは言えない」ことも、本音と建て前の乖離なのだ。戦争技術者である軍人たちが「ダメです。何をどうしても勝てません」と本音を明言できたならば、政治家らはそれに対応して新たな日本の進路を模索できたかもしれない。
身も蓋もない本音を明確に口にして、共有の知識とし、議論の前提とする仕組みが、戦前日本には欠けていた。この欠如が、正気で理性的な現状認識と行動から、狂気を絞り出すフィルターとして機能していたのである。
さらに、軍人たちは軍人であるが故に「そもそも戦争をしない/次の総力戦に巻き込まれない日本を作る」という選択肢を想像することすらできなかった、ということも指摘できるだろう。
満州国を作ることで経済成長を志向した石原莞爾にしても、経済成長はあくまで彼の想定する世界最終戦争という総力戦を勝利するための道具だった。
「経済成長によって長期の平和を維持する」という発想はなかった。彼は、なんの証拠もなく、世界最終戦争は日本とアメリカの戦いになると信じ込んでいた(敗戦後、石原はそれが誤りであったと反省している)。しかし、例えばアメリカとの戦争を回避するための経済成長というのもあり得たかもしれない。日本と満州国の経済成長が、アメリカにとっても利益となるものへと持っていけば――満州の工業化にアメリカ資本を大規模に導入するとかしていれば――あるいは、対米戦争そのものを回避できたかもしれない。
本書は、真っ当な頭脳と冷静な正気から、狂気が導き出される過程を露わにした。さあ、私たちはこれを教訓として未来に向かわねばならない。
例えば、関係各国がすべて正気で合理的な判断をした結果、北朝鮮を巡る有事が勃発するというような事態は、なんとしても避けねばならないのだ。
【今回ご紹介した書籍】
『未完のファシズム −「持たざる国」日本の運命丸−』
片山杜秀 著/四六判変形/346頁/定価1650円(本体1500円+税10%)/2012年11月刊行/
新潮社/ISBN 978-4-10-603705-4
http://www.shinchosha.co.jp/book/603705/
※電子書籍版もあります。
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2017
Shokabo-News No. 338(2017-9)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在、日経ビジネスオンラインで「宇宙開発の新潮流(*1)」を、「自動運転の論点」で「モビリティで変わる社会(*2)」を連載中。近著に『母さん、ごめん。−50代独身男の介護奮闘記−』(日経BP社)がある.その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数.
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
*1 http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20101208/217467/
*2 http://jidounten.jp/archives/author/shinya-matsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 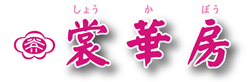
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム 