第40回 自動車メーカーを建て直した透徹したリアリズム、
柔らかいリアリズム
山中浩之 著『マツダ −心を燃やす逆転の経営−』(日経BP社)

最初にお断りを。「絶版でも古い本でもいいので、お好きな本を紹介してください」ということで楽しく続けさせてもらっているこの連載だが、今回取り上げる本は、ちょっと事情が異なる。
著者の山中浩之氏は、実は日経ビジネス編集部の私の担当編集なのだ。その山中さんが、自動車メーカーのマツダ元会長である金井誠太氏に2年半あまりの時間をかけてインタビューを繰り返し、周辺取材を固めてまとめたのが、この本だ。テーマはマツダの再生。1992年のバブル経済崩壊後に会社としてまさに地獄を見たマツダが、どうやって復活してきたかを、金井氏のインタビューを通じてまとめている。
というわけで、ここで紹介する理由の一つは、山中さんが「松浦さん、どっかで紹介してください(でないとあんたの日経ビジネスの連載をごにょごにょ……)」と言ってきたからだ(もちろん、裳華房K氏の了解は取った。取りましたとも)。が、もちろんそれだけではない。これがもう、大変に面白いのである。特に自動車のみならず、メカニズム全般に興味のある方はたまらないだろう。と同時に、面白いが故の、本の作り方の問題点も透けて見えてくる一冊でもある。
まず、マツダがバブル崩壊でどうなったか──広島に本社を置く自動車メーカーのマツダは1920年創業。戦前の三輪トラック製造から自動車の製造販売に参入し、1960年には「R360クーペ」で一般向け乗用車の製造を開始。1967年には今でもマツダを象徴するともいえるロータリーエンジン車「コスモスポーツ」を発売した。1980年代には一般向け乗用車「ファミリア」の大ヒットなどで業績を伸ばし、積極的な拡大路線をひた走った。1991年にはルマン24時間耐久レースで、ロータリーエンジンを搭載したレース車「マツダ787B」で総合優勝するという快挙を成し遂げている。
ところが、1991年のバブル景気崩壊後の経営を決定的に誤った。バブル時の感覚のまま押し進めた積極的な販売攻勢と新車開発が思いきり裏目に出て業績は低迷、1994年には赤字に転落。1996年には米フォード・モーターの支援を受けることとなり、フォード傘下に入る。
いけいけどんどんのバブル景気から一転しての“マツダ地獄”、その渦中で静かに「マツダのものつくりのやり方を決定的に変えなくてはいけない」という動きが始まっていた。その中心人物が、車体設計エンジニアであった金井誠太氏だった。
本書は「マツダは個性的な自動車を作ってきた」という話から始まる。しかし、ここしばらくのマツダ車はどれも似た雰囲気ではないか、と突っ込む山中さんに、金井氏は「40年かけてそうしてきたんだ」と語る。
かつてのマツダは個性的であることを社内で競ってきた。結果、車種ごと、モデルチェンジ毎の振れ幅が大きくなりすぎて、「これがマツダ車だ」という大きな個性を押し出すことに失敗したというのである。
「これがマツダ車だ」という個性は、外見や内装のデザインからだけでは生まれない。根本に「クルマはかくあるべき」という理想と哲学があり、それらを実現する技術と設計が確立している必要がある。技術と設計がうまく回ることで、理想と哲学を体現する基本プラットホーム(シャーシとかエンジンとかの、自動車の根幹のこと)が作れる。基本プラットホームを各車種に展開していけば、そこに「これがマツダ車だ」という個性が生まれる──このような理想・哲学から製品に至るまでの流れを作るために、金井氏は1980年代末から30年以上の時間をかけることになった。
かつてのマツダの開発体制を語る第一章は、「考えなしで走ってはいけない」というごく当たり前の教訓に収束する。新車開発を始める前に十分に考えておくこと、「トラブルが起きたら解決する」ではなく、「事前に徹底的に考えておくことが重要だ」というのだ。ただし、金井氏は「考えたけれどやってみたら間違っていた」ということを非難しない。
金井 大事なのは根拠を明確にして、「決める」ことです。そして「いつ、誰が、どういう理由で決定したのか」を明記しておく。責任を問うためじゃないですよ。「誤った決定に至ったのは、どの前提が変わったからなのか」がすぐ分かり、修正するポイントも明確になるからです。「考えて間違うこと」は、罪じゃない。「考えないで始めること」と、「間違えても手を打たないこと」が罪なんです。
(本書第1章末尾「Colum「火消し」を仕事と考えてはいけない」より)
この言葉が示すのは、透徹したリアリズムだ。
私たちは時として「ぎりぎりに追い詰められてからの逆転劇」を好む。忘れてはいけない、NHKにかつて『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』という実録ネタを取り上げる看板番組があった。後半に「ここから男達の逆転が始まります」というナレーションが入って逆転劇を強調する演出を施し、高視聴率をマークして、番組は5年9か月も続いた。マツダも同番組に「ロータリー 47士の闘い 〜夢のエンジン 廃墟からの誕生」という大仰なタイトルで登場している。
が、逆転劇があるということは「劣勢の時期があった」ということだ。それはつまるところ、事前の思考の不足が招いた失敗なのである。最上の勝ちパターンは「最初から最後まで優勢にことを進める」ということなのだから。逆転のカタルシスは、事前の思考の不足という失敗を覆い隠してしまう。
『プロジェクトX』は、結局、実録ネタの枯渇から事実の偽造に走り、非難を浴びて番組終了となった。最後は「プロジェクト×(ペケ)」などと揶揄されていたのを覚えている方もいるだろう。
金井氏の言葉を同番組に適用するなら、なぜ事前に「逆転の実録ネタなどそうそうあるわけない」というところまで考えていなかったか、ということになるだろう。そして、そのことに気が付いた時に、なぜ番組を休止するという判断をせず、事実の偽造に走ったかという反省点に行き着くだろう。
さらに、根本には「なぜみんな逆転劇が大好きなのか」「逆転のカタルシスで実録番組を構成することは正しいのか」という思考があるべきだろう。私が──と限定して語るが──この思考をたどって得た結論は、「プロジェクトXのような逆転のカタルシスを狙った実録番組は最初から、毎週放送する帯番組として続けて作るべきではなかった」である。それは一発ものなのだ。
話が逸れてしまった。
本書はこの後、フォード傘下に入り、同社の世界戦略の範囲内での新車開発をせざるを得なくなった状況で、マツダがどのようにして独自性を押し出していったかという話に展開する。金井氏、そして彼の周囲に集まった技術者たちは自動車設計をデジタル化し、シミュレーションから製図、工作機械を動かす製造データやプレス用金型の図面の作成までをひとつの流れとして行うシステムを作る中で、自動車を開発するという仕事の流れを「理想と哲学から製品へ」という一貫性を持ったものに作り替えていく。
その途中で、マツダ復活のきっかけとなった新車「アテンザ」開発のエピソードが挟まったり、「理想から製品へ」を実現するために生産現場を改革する話が出て来たり、今やマツダの看板となったSKYACTIVエンジン技術の開発経緯に言及したり──会社の置かれた状況の中で、金井氏が具体的にどのようにして物事を進めていったかが語られる。
このあたりは金井氏の個性が非常に強く出ている。それは「透徹したリアリズム」に対して「柔らかいリアリズム」とまとめることができるだろう。透徹したリアリズムには身も蓋もなく現実を見つめるという意味があるが、対して柔らかいリアリズムは「人」という要素を加味したリアリズムだ。身も蓋もない真実を突きつけられた時、人は様々な反応をする。あっさり認める人もいるし、ふてくされる人もいるし、逆にむきになって反論する人もいる。金井氏は、そういった人の反応を見極めつつ、全体を理想に向けて結束させ、方向付けていく。
氏の柔らかいリアリズムは、柔軟な発想法としても具体化する。特に第6章末尾に附属する「Column 二律背反の乗り越え方」にまとめられている金井氏の発想法は、「その手があったか」と驚く読者も多いのではないだろうか。実際の商品開発の現場で「コスト低減か、それとも性能か」というような二律背反を迫られた時に「コストも下げて性能も上げる」ためにはどのように思考すればいいか、という経験から導き出された手法だ。
2008年に起きたリーマンショックで、またもマツダは大きく揺さぶられた。収益は減少し、親会社であたフォードは段階的にマツダの株式を売却して撤退した。その中でもマツダは技術開発の投資を続行した。
1980年代に始まる同社の改革は、今やラインナップとして結実している。実際、ひとりの乗り物好きとして、現在のマツダ車はどれも魅力的と感じている。「デミオ」は本当に良くできている。「ロードスター」は一日借りて試乗したが、惚れ惚れするほど走るのが楽しいクルマだった。今年、2019年になって発表された「マツダ3」は見事なまでに無駄がなく美しいデザインをしている。
──というわけで、本書は出版タイミングも良く、実に「めでたし、めでたし」という構成になっているのだが、ひとつ大きな不満がある。
中味が足りないのだ。
マツダのようにそれなりに大きな会社は、けっして一人の人間の能力だけで動かすことはできない。30年以上に渡る同社の改革は、金井氏ひとりだけではなく、何人もの人が協力して成ったものだ。それを金井氏ひとりに代表させるのは無理があるのではないか。本書には、藤原清志・現副社長のインタビューも収録されているのだが──それでもマツダの歩みの全貌を概観するのには足りない。
そのあたりを山中さんに聞くと、金井氏以外の人たちへの取材もがっちりとやったという。「しかし、一冊の本に入りきらないんです」──というわけで、現在「日経ビジネス電子版」にて
『モノ造り革新』のリアル−マツダ復活の証言
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00049/
という“はみ出した部分”の連載が始まっている。
私としてはこれが気に入らない。これは、本の組版を2段組みにしてでも、1冊の本に詰め込むべきではないか。実際、翻訳のノンフィクションはそのような体裁のものが少なくない。
「ダメなんですよ」と山中さん。「2段組にすると、とたんに本の売れ行きが落ちるんです」。
この数十年、日本の出版物は一貫して「読みやすさ」を追求してきた。文字は大きくし、1ページに入る文字数を減らし、ページ数もあまり多くはせずに1日で読み切れる程度の文章量にする、というように。しかし、そのことが本の内容を薄くしてはいないだろうか。
薄くなった内容に慣れてしまった読者は、ぶ厚い圧倒的な情報量の本を敬遠するようになる。「読みやすく」を追求し続けた結果、日本語出版物は、知的耐久力と情報咀嚼力に優れた読者を失いつつあるのではないだろうか。
面白い良い本だ。しかし、本筋だけでなく周辺も含め一冊で読ませろ──私にとってはそういう本である。
【今回ご紹介した書籍】
『マツダ −心を燃やす逆転の経営−』
山中浩之 著/四六判/370頁/定価1760円(本体1600円+税10%)/2019年5月発行/
日経BP社/ISBN 978-4-296-10089-7
https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/19/270960/
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2019
Shokabo-News No. 355(2019-6)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在、日経ビジネスオンラインで「宇宙開発の新潮流(*1)」を連載中。近著に『母さん、ごめん。−50代独身男の介護奮闘記−』(日経BP社)がある.その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数.
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
*1 http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20101208/217467/
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 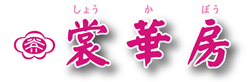
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム