第44回 ウイルスを巡るリアリティ、知識、偶然、そして人類への信頼
小松左京 著『復活の日』(角川文庫/ハルキ文庫/早川書房)

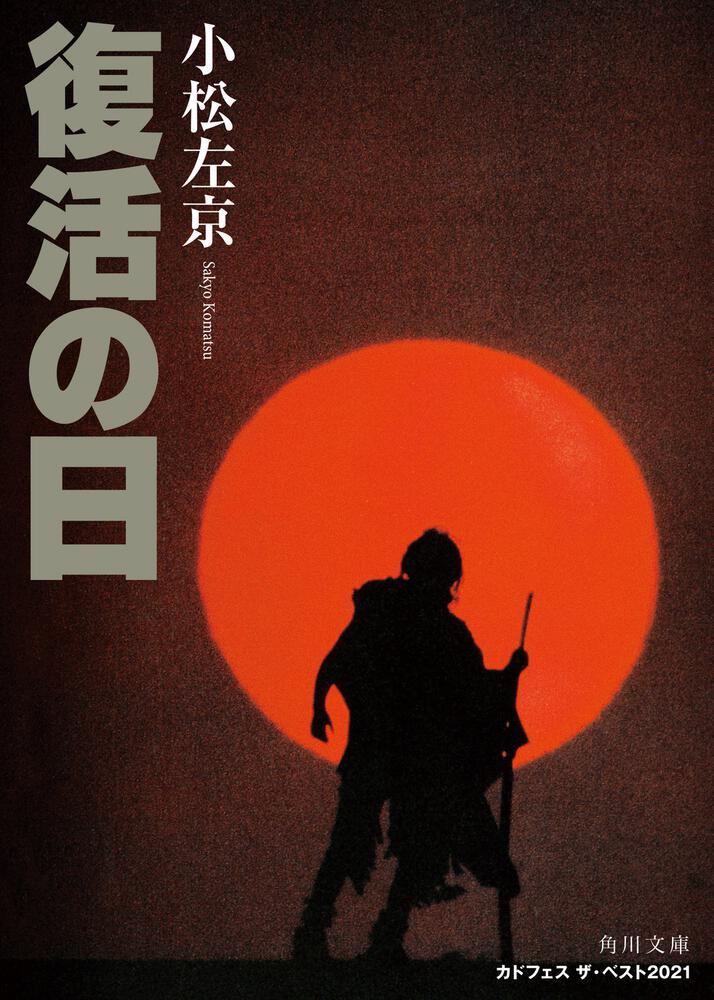
前回のこの連載のテキストファイルには2019年12月23日というタイムスタンプがついていた。
その時点では、こんなことになるとは思ってもいなかった。新型コロナウイルスCOVID-19によるウイルス性肺炎のパンデミックである。
厚生労働省ホームページを見ると、「中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について」というアラートが出たのは今年の1月6日だ。その時点で「昨年12月以降、原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されています。」と書かれている。
その10日後の1月16日には、「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(1例目)」と、日本国内での最初の患者が報告され──そこからは皆さんご存知の通りだ。この原稿を書いている3月27日の時点で、日本における累計感染者数は1349人、発症した患者数は1191人、死亡者数46人である。全世界では感染者数51万6044人、死者数2万2687人。この数字は、記事が読者の皆さんに届くまでに、また増えていることであろう。それも半端なく。
発生地である中国はどうやら制圧に向かいそうだが、イタリア、スペイン、アメリカ、イランで急速に患者数が増えている。
そこで思わず本棚から引き抜き、手に取ってしまったのが小松左京著『復活の日』であった。1964年に出版されたパンデミックSFの傑作だ。極秘裏に開発された生物兵器が、人類はおろか哺乳類のほとんどを滅ぼしてしまい、南極の観測基地にいた少数の人々だけが生き残るが、そこに東西冷戦体制の亡霊が新たな危機をもたらす、という内容である。
もう50年以上昔に書かれた小説だけに、いくつかの部分の内容は古くなっている。が、全体は驚くほど古びておらず、新鮮だ。否、新鮮どころか、現状を重ね合わせると、今現在の問題として捉えることすら可能だ。
『復活の日』は、第一部「災厄の日」、第二部「復活の日」の二部構成だ。パンデミックによる人類絶滅を描く第一部が全体の約8割を占めている。
今回改めて読み返して、まず、物語冒頭の掴みの見事さにびっくりしてしまった。
ブロー!」艦長のマクラウド大佐がいった。
「はい、艦長(ダー カピタン、とルビあり)……」赤毛で獅子っ鼻のイワン・ミハイロビッチ兵曹は、わざとロシア語でこたえて、ニヤッと笑った。
(『復活の日』「プロローグ 1973年3月」より)
ロシア(執筆当時はソ連だが)の軍人にアメリカの軍人が命令する──たったこれだけで、なにか途方もないことが起きていることを読者に伝えるのだ。読み進めると、舞台は米海軍の原子力潜水艦ネーレイド号の艦内であり、同艦は東京湾を目指して海中を移動中であることが見えてくる。潜望鏡から見える日本の風景から徐々に判明する事態。人類はごく少数を残して滅亡したのだった。
そして、物語は数年前の冬のイギリスへと移る。生物兵器の研究者であるグレゴール・カールスキイ教授が何か大変に危険な国家機密を持ち出し、怪しい男たちと取り引きをする。教授は男たちに、その「危険物」への対抗策を作れるライゼナウ教授に渡すように頼むが、男たちにとってそんなことは知ったことではない。別の何者かにその危険物を売り飛ばすべく、悪天候の中、航空機で高飛びしようとして、アルプスに墜落する。そして春になり雪が解けて、アルプスにほど近い高速道路でスーパーカーを運転していた二枚目俳優が奇怪な事故を起こす──。
カールスキイ教授が持ち出したのはMM-88という生物兵器だった。彼は途轍もない凶悪な兵器を作り出してしまったことに悩み、治療法を開発できそうな知人にサンプルを渡そうとして、失敗したのである。航空機事故で外界に出たMM-88は、雪解けとともに増殖を開始し、あっという間に人類を滅ぼしてしまう。なにしろ4か月後の7月には、死者多数で世界各国の政府組織が崩壊し、夏を過ぎた9月には、もう南極を除いて人類、それどころかほぼすべての陸上哺乳類は絶滅しているのである。
人類絶滅のプロセスは、小さなエピソードを多数連ねていくことで語られる。カンザス州の養鶏場で起きる七面鳥の雛の大量死。新型インフルエンザ「チベットかぜ」の発生。米国防総省、あるいはロンドンの英陸軍省で交わされる秘密の会話。東京下町の病院に殺到する患者たち。ありとあらゆる手段を使って増産されるが、なぜか効かない「チベットかぜ」のワクチン。人類は真の敵、チベットかぜのウイルスに隠れて拡散するMM-88に気が付くことができない。そして6月に入ると、街角に死体が出現しはじめる。MM-88は神経を侵食し心臓麻痺を起こすのだ。最初のうちは片付けられていた死体も、社会の崩壊とともに放置されるようになる。
あれよあれよと進行する人類社会崩壊の様子を、南極の冬を過ごす各国の越冬隊は、無線通信越しに知ることとなる。
本書の特色は、四つあると思う。まず「リアリティ」。
コロナウイルスによるパンデミックが進行中である現在、本書を読んでまず感じるのは、不気味なほどの現実との対応だろう。感染拡大初期の根拠なき楽観と、指数関数的な事態の一気の悪化、ラッシュ時間帯なのに空いている通勤電車、株式市場の暴落、興行・公演の中止、外国の首脳の罹患(本書ではさらに踏み込んで、首脳の死亡まで書き込んである)、「戦争も同然」の状態となる病院、自衛隊の出動──嫌になるほどリアルである。
次が「膨大な知識」だ。
小松は、破滅していく世界を描写するために、ありったけの知識と知見を積みかさねていく。MM-88という架空の生物兵器が人命を奪う機序(これは見事に医学の知見を踏まえた上でのSF的飛躍だ)から、朝鮮戦争時に米軍が旧日本陸軍731部隊の協力を得て細菌戦を展開した史実(これには様々な異論があるが、いろいろと資料を漁るに事実であったのだろうと思わせる)、危うかった冷戦時代の核兵器管理の実態(冷戦まっただ中の1964年に、よくこれだけ調べ上げたものだ)などなど……理系文系を問わない分厚い知識が、破滅へ突き進む描写を裏打ちしていく。
三つ目が「偶然」だ。
人類絶滅は、小さな偶然の連鎖で進行していく。圧巻は英陸軍省で交わされる、生物兵器開発に関する会話である。絶望したカールスキイ教授は自殺し、事態を重く見た英陸軍省幹部は、カールスキイ教授の研究を知るランドン博士を訊問する。彼らは、あと少しでMM-88が外部に漏洩したという真実に到達しそうになるが、ほんのちょっとした会話の綾で、気が付くことができない。
本連載でも何回か、歴史の流れが本当に小さな偶然で左右される様子を紹介したが、本書における人類絶滅も不幸な偶然の連鎖で進行していくのである。
そして、もっとも強調すべきは──これは非常に逆説的なのだが──人間という生き物、人間が持ち得た理性に対する「信頼」だ。
なかでも、ヘルシンキ大学のユージン・スミルノフ教授が行う“最後の授業”は、『復活の日』全編の中でもっとも重要な部分ではなかろうか。このエピソードは、おそらく通常のエンタテインメント小説だとカットされるはずだ。それほど本筋から離れていて、唐突感は否めず、にもかかわらず長く冗長である。まるで、オペラにおいて瀕死であるはずのヒロインが延々と大声でアリアを歌うかのような不自然さに溢れている。にもかかわらず、スミルノフ教授の独白は大変感動的なのである。
スミルノフ教授は滅び行く人類を人文科学的に総括する。その矮小さ、愚かさを嘆き、知識人として事態の展開になすすべがなかった自らの卑小さを悔いる。ところが小松は、スミルノフ教授に「それは……むしろ、未来における課題であったかもしれません」と語らせる。
この小説の読者は、小説内の破滅とは無関係だ。エンタメとしての小説を読んでいる。だから、物語の中のスミルノフ教授が破滅に際して人類が解決すべきであった課題を総括し、深く悔いるほどに、読者の側は「これらの問題に取り組めば人類の未来は明るいのか」と思えてくるのだ。
もうひとつ、著者の人間観が出ているなと思えるのは、MM-88の機序を独自に解明し、その知識を南極に伝えて人類絶滅をぎりぎりで回避させることに成功したA・リンスキイという医師が、これほど重要な役割にも関わらず、物語には一切登場しないということだ。リンスキイがどのようにしてMM-88に気が付いたかのプロセスは、まるでパズルの断片のように物語の中にはめ込まれている。しかし、リンスキイが何を考えるどんな人物であったかは一切描かれない。彼は、自分の研究成果をエンドレステープに吹き込み、アマチュア無線を通じて世界に伝わるようにして死ぬ(今なら、論文をarXiv.orgに投稿であろう)。そのため彼は、名前ですらなく、WA5PSというアマチュア無線のコールサインで生き残った人々に記憶されることになる。
本物の危機にあたって、重要で意義ある事を為すのは、社会の表で偉そうにしている者ではない。名もなく地味に、社会の各所で己の責務を果たしている有能な人々こそが、世界を救う。作者はそのような人々にこそ、未来への希望を見ているのである。
第二部「復活の日」では、南極の生き残りに、滅亡した人類社会が後に遺した憎悪の刃が迫る。恐怖と憎悪が仕組んだ「人類二度目の死」を食い止めるために、4人の決死隊がモスクワとワシントンD.C.に赴く。ここまで小説を支えて来た要素──リアリティ、膨大な知識、偶然、そして知性・理性への信頼が一気に絡まり、盛り上がり、あの有名なラスト、南米大陸南端での劇的な再会に至る。
1980年に公開された映画版(深作欣二監督)では、印象的かつ感動的な、登場人物の一人である吉住の北米から南米にかけての彷徨は、原作ではたった2ページで記述されている。このことは、もっと注目されてもいいだろう。小松左京にとっては、ひとたび知のパースペクティブが構築されてしまえば、個々のエピソードは詳述しなくても、自ずと読者に伝わるものだったのであろう。
COVID-19のパンデミックは、今後どのような推移をたどるのか。
私自身はかなり甘く見積もっていたと白状しなくてはならない。2月27日に安倍首相が学校の全校休校を要請した時点で、「それはやり過ぎだろう」と考えていた。むしろ一般の会社の50歳以上を出勤停止にするべきと考えていた。一気に人出が減ったのを見て、「今年は人っ子一人いない満開の桜を楽しめるかも」とか考えていた。
「これはまずい」と緊迫感を覚えたのは、3月20日〜22日の三連休で、人々の警戒感が緩み、一気に人出が増えた時だった。まだ警戒を解くのは早すぎる。こんなことをしていると爆発的な感染拡大が起きるぞ、と思った。
実のところ1月、遅くとも2月半ばの時点で、何が起きるかは自明だった。COVID-19は、新しいウイルスなので誰も免疫をもっていない。しかも高齢者と基礎疾患をもつ者ほど致死率が高まる。また、感染から発症まで4日から2週間程度あり、しかも症状の出ない不顕性感染があり得る。つまり、大変感染拡大しやすく、いったん拡大すると高齢者と基礎疾患をもつ者とで多数の死者、重症者が発生する。大変厄介で恐ろしい特性をもっているウイルスなのだ。
取り得る手段は、第一に日本への侵入阻止。しかし、これは失敗した。感染から発症までの間隔が長く、無症状の感染者が移動するからだ。
次は、とにかく感染拡大を防ぐこと。現状の「クラスター(誰から感染したかが分かる、一群の感染者の塊)を見つけ、つぶす」というのがこの状態である。目的は医療崩壊を防ぐことだ。重症者は重篤な肺炎のために人工呼吸器や、血液に直接酸素を送り込む人工心肺が必要になる。これらの装置の数は限りがある。重症者数が、装置の数を超えると助かる命も助からなくなる。
クラスターを潰して感染確率を下げていくと、やがてパンデミックは終息する。あるいは患者発生を止められなくとも、ワクチンなどの開発が間に合えば、そこでパンデミックは終わる。
もう一つのシナリオが、感染拡大が続き、爆発的に患者が増えた場合の集団免疫の確立だ。
感染が拡大すると多くの人が免疫を獲得し、社会全体の感染確率が下がってパンデミックは終息する。これが「集団免疫の確立」だ。構成員の6割が免疫を獲得すると集団免疫が確立する。
もしも自然状態で感染拡大が野放しになったとしよう。日本人口は1億2680万人なので、その6割は7600万人。これらの人が軽度の感染で免疫を獲得する必要がある。仮に致死率が2%とすると、約152万人が死ぬということになる。1%としても76万人だ。東日本大震災(死者・行方不明者1万8456人)の40倍以上だ。
これは決して大げさな見積もりではなく、1918年から20年にかけてのスペインインフルエンザのパンデミックでは、日本の総人口が5500万人の当時、3年間で約45万人が死亡したと推定されている。
スペインインフルエンザもまた、誰も免疫を持っていない新ウイルスの疾患であり、集団免疫の確率による流行収束に3年かかった。つまり、そのままCOVID-19に当てはめると、放置した場合は70万人以上の死者を出しつつ2023年以降に収束するということになる。
したがって、このパターンで死者を最小に留めつつパンデミックを乗り切るには、現在のクラスター潰しを続けて、医療崩壊を防ぎつつ時間を稼ぎ、薬やワクチンの開発を進めて、ワクチン一斉接種で集団免疫を確立する必要がある、ということになる。
行政府が発している「出歩くな」という強いメッセージには、以上のような意味がある。
しかし、外出しないことには経済が回らない。経済状況が悪化すると、今度は経済苦境からの自殺者が増える。政府は超大型の財政出動を行って経済を支えつつ、中期的には「外出なしでも回る経済体制」をつくる必要がある。
ワクチンの開発には12か月から18か月がかかると報道されている。事前に大量生産の手配を進めておくにしても、そこから量産し、一斉に接種し、集団免疫が確立するには、さらに1年ぐらいは見込む必要があるだろう。
クラスターを潰し続けることで収束するか、それとも集団免疫の確立で収束するか──いずれにせよ「スペインインフルエンザの先例を見る限り、これは長期戦になるな」というのが私の見通しである。先だって、東京五輪は「1年程度の延期」を決めたが、私が正しければ延期は1年では済まないだろう。おそらく東京五輪は中止になるはずだ。
小松左京は『復活の日』で、愚行から滅亡する人類を描きつつも、同時に人類がもつ知性・理性への強い信頼をも訴えた。
COVID-19で問われるのは、安倍晋三首相以下の日本の政治、厚生労働省を初めとした行政府、そして我々国民の、知性と理性である。理性と知性に基づく行動のみが、このパンデミックを収束に導くのだ。
【今回ご紹介した書籍】
『復活の日』
小松左京 著/文庫判/464頁/定価836円(本体760円+税10%)/2018年8月新版発行/
KADOKAWA(角川文庫)/ISBN 978-4-04-106581-5
https://www.kadokawa.co.jp/product/321710000583/
※電子版も発売中。
『[新装版]復活の日』
小松左京 著/文庫判/456頁/定価880円(本体800円+税10%)/2018年8月発行/
角川春樹事務所(ハルキ文庫)/ISBN 978-4-75844164-3
http://www.kadokawaharuki.co.jp/book/detail/detail.php?no=5753
『復活の日(新版)』
小松左京 著/四六判/380頁/定価2530円(本体2300円+税10%)/2018年1月発行/
早川書房/ISBN 978-4-15-209738-5
 ※上記以外に、新井リュウジが児童向けにリライトした『復活の日 −人類滅亡の危機との闘い−』が2018年にポプラ社より刊行されています。
※上記以外に、新井リュウジが児童向けにリライトした『復活の日 −人類滅亡の危機との闘い−』が2018年にポプラ社より刊行されています。
https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4052011.html
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2020
Shokabo-News No. 361(2020-3)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在、日経ビジネスオンラインで「宇宙開発の新潮流(*1)」を連載中。近著に『母さん、ごめん。−50代独身男の介護奮闘記−』(日経BP社)がある.その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数.
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
*1 http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20101208/217467/
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 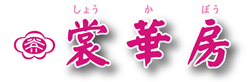
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム