第54回 満洲を巡る野望と夢
『阿片王 −満洲の夜と霧−』(佐野眞一 著、新潮社)
『甘粕正彦 −乱心の曠野−』(佐野眞一 著、新潮社)
『佐野眞一が殺したジャーナリズム』(溝口敦・荒井香織 編著、宝島社)
さて、「満洲で阿片を商うことで得られた闇資金は、戦後日本政界に流入したのか」という安楽椅子探偵の続きだ。
この問題を考えるには、阿片ビジネスで金を作る側だった、里見甫(1896〜1965)と甘粕正彦(1891〜1945)をきちんと押さえておく必要がある。この場合、問題になるのは里見のほうだ。甘粕は、関東大震災後の混乱に乗じて無政府主義者の大杉栄(1885〜1923)、伊藤野枝(1895〜1923)、さらには大杉の甥の橘宗一(1917〜1923)を殺害した甘粕事件で有罪となった有名人であり、関連書籍も多い。一方、里見はといえば、ひっそりと歴史のひだの中に身を隠した感があり、情報が少ない。
うまくこの2人を概観できる本はないかと探すと、佐野眞一氏の2冊が見つかった。出版年代からして、明らかに連続して取材をし、執筆されたものだろう。
ところが佐野氏は、2012年に著書中の盗用が発覚したことがきっかけで、過去の様々な盗用が表沙汰となり、その後鳴かず飛ばずとなってしまった。したがって、この2冊についても、まずこれらがどの程度の信用のおける本なのかという当たりを付ける必要がある。
そこで読んだのが、佐野氏の盗用を詳細にまとめた『佐野眞一が殺したジャーナリズム』だ。この本を読んで、どうやらこの2冊には問題なさそうだと判断したので、ここで紹介する次第である。なお引用のページ数は文庫版ではなく、単行本版に依る。
 まず『佐野眞一が殺したジャーナリズム』だ。
まず『佐野眞一が殺したジャーナリズム』だ。
佐野氏は、2012年10月に週刊朝日に掲載した「ハシシタ 奴の本性」がきっかけとなり、次々に過去の盗用が明るみに出た。過去の被害者複数が佐野氏から受け取った詫び状を公開したのだから、相当に被害は広く深く、「あの野郎ふざけたことしやがって」という怨念が鬱積していたのだろう。本書には、佐野氏著書における盗用が一覧表として掲載されており、その中に里見と甘粕に関する著書2冊は入っていない。
実のところ、私はこの盗用の話が持ち上がった時、「なるほど」と思ったのだった。というのも、佐野氏の執筆の速度は私の感覚からするとあまりに速く「どうやって、そんな速度で取材、資料読み込み、執筆ができるのだろうか」と感嘆し、かつ「あの速度で書けない自分は無能だ」と思っていたのである。ノンフィクションというのはとにかく手間の掛かるものだ。関係者に取材に行き、ありとあらゆる手段を使って資料を集め、さらに付き合わせて妥当と思われる事実を抽出し、やっと執筆することができる。佐野氏の執筆速度が大量の盗用で成立していたとすると、感覚的に納得がいく。
他方で、いくつかの佐野氏の著書は、実際に人に会い、足でしか稼げない情報が詰まっているとも感じていた。盗用の事実とは別に、佐野氏は一つひとつは実りの少ない取材を延々と続けて、集めた貴重な情報から、ひとつの構図を描き出す能力もあるのだ。今回紹介する2冊は、私からは「地道な取材をずいぶんと重ねた労作」と見える。
 『甘粕正彦 −乱心の曠野−』から行こう。本書の眼目は「前途洋々だったはずのエリートが、あまりに真面目であったが故にたどった茫漠たる精神の荒野」だ。
『甘粕正彦 −乱心の曠野−』から行こう。本書の眼目は「前途洋々だったはずのエリートが、あまりに真面目であったが故にたどった茫漠たる精神の荒野」だ。
甘粕は、上杉謙信家臣団の一員で「上杉四天王」のひとりと謳われた甘粕景持の子孫という名家に生まれた。陸軍士官学校を卒業し、陸軍の花形である歩兵科に所属するが、膝を怪我したことがきっかけで出世コースという面では“裏道”である憲兵に転ずる。そこで甘粕事件が起きたことで、彼の人生は裏街道へと一気にねじ曲がってしまう。
私は知らなかったのだが、現在、甘粕事件において、甘粕正彦は大杉らの殺害に直接手を下していないという説が主流になっているらしい。というのも、戦後になって大杉らの検死報告書が発見され、裁判における甘粕の証言と矛盾することが分かったからだ。検死報告書には、大杉、伊藤は激しく暴行された後に殺害されたと指摘していた。しかし、甘粕は裁判で暴行について一切述べていなかった。明らかに甘粕は何かを庇ってあえて罪を被った──この見立てで本書は展開する。
甘粕が何の罪を被ったかは、事件後の彼の人生をみていくと明白だ。彼は所属する日本陸軍の罪を被ったのである。当時の陸軍内部には、なにかあったら無政府主義者を暴力的に排除してしまえという雰囲気があった。この雰囲気が関東大震災とそれに続く戒厳令布告で、暴走した。本書では断定していないが、甘粕と同時に起訴された森慶次郎、平井利一、本多重雄、鴨志田安五郎という憲兵隊下士官らが直接手を下したことで間違いないだろう。
そこに軍の指揮系統に基づく命令があったかどうかだが、これはわからない。裁判で一貫して罪を被ろうとした甘粕の行動からして、あった可能性は高い。とすると、大杉ら3人を殺害した罪は末端の下士官のみならず日本陸軍全体にかかる。
その一方で、幼い橘宗一までも無惨に殺害し、3人の遺体を古井戸に投げ込んで始末したという犯行の雑さからは、軍のような組織が行う計画的犯罪というよりも、震災の雰囲気に乗って暴走した庶民、すなわち下士官らの犯罪という雰囲気が漂う。そもそも森以下の下士官らは、指揮系統上は甘粕の命令を受ける立場ですらなかった。
罪を被った甘粕を陸軍は無下にできず、かといって重用もできない。出獄後に欧州留学に出すなどの優遇をしつつも、結局満洲に追いやる。満洲で甘粕は謀略という生き甲斐をみつけ、「甘粕事件の首謀者」という虚名をも利用して、怪物と化していく。
阿片と金という面で本書を読んでいくと、まず1931年(昭和6年)の満洲事変では、甘粕は自ら清朝皇帝愛新覚羅溥儀の保護に動き、さらには自らもハルピンの日本総領事館に爆弾を投げ込むというテロ行為に参加している。金があれば自分で危ないことをする必要はない。つまり満洲事変の時点では、甘粕はまだ阿片という金蔓を掴んでいない。ではどこで掴んだのか。
満洲国成立で同国の官吏となった甘粕は、1934年(昭和9年)に大東公司という会社の設立に関わった。この会社は満洲国成立で起きた建設ブームに対して、良質な土木労働力を中国(中華民国)から満洲国に入れることを目的としていた。つまりは苦力の口入れ屋である。甘粕は直接社長に就任するのではなく、同社を仕切る裏の実力者のポジションを得た。
本書には、五十嵐八郎という方の以下のような証言が掲載されている。
「関東軍は東京の参謀本部のいうことなどまったく聞かなかった。それは甘粕と里見という潤沢な資金源があったからだよ。甘粕は苦力の口入れ屋でピンハネした金を、里見は阿片で稼いだ金を、それぞれ関東軍にせっせと貢いでいたんだと思う。甘粕と里見は人間のタイプは全然違うが、その金を自分のポケットに入れなかったことでは二人とも共通していた。だからよけい関東軍に信用されたんだろうな」(同書p.297)
おそらくこれだ。「当時はクーリーには塩と阿片が不可欠だった」という『阿片と大砲』の記述を思い出そう(本コラム第27回参照)。甘粕がどこから阿片を仕入れたかは不明だが、大東公司経由で満州国内に入れた苦力に供給したとみて、ほぼ間違いないだろう。大東公司は、満洲国入りする中国人苦力の選別を行い、彼らから手数料を徴収し、さらには彼らを建設の現場に紹介していた。中国人苦力は、ソ連・満洲国境地帯の要塞や、満洲の電力需要を満たすために松花江(スンガリー川)に建設された豊満ダムの建設現場に送り込まれた。そんな満洲国・関東軍が仕切る建設現場に甘粕と大東公司が阿片を供給していたと考えると、辻褄が合う。
あるいはその現場に、飛田勝造も関わっていたのかも知れない(第51回参照)。が、これは推測の域を出ない。
そうして得た金で甘粕が展開したという謀略だが、本書の記述を読む限り、むしろ満洲の外、東南アジア方面が主だったようだ。甘粕は日本主義、さらにはアジア主義を主張して戦前大きな影響力をもっていた思想家・大川周明(1886〜1957)に心酔していた。大川の主張は、アジアは団結して欧米列強に対抗すべしというもので、広大な植民地をもつイギリスへの反感が色濃かった。本書に出てくる、唯一甘粕が生前に語った謀略は、英領シンガポールで行ったものなのだ。1938年(昭和13年)、甘粕は欧米訪問使節団に参加するのだが、この時彼はシンガポールで入国を拒否されている。それについて彼は「昔、ちょっとシンガポールでいたずらをしたので」と語った。
1939年(昭和14年)に満洲映画協会(満映)理事長に就任してからの甘粕は、むしろ有能辣腕の経営者の印象が強い。放漫経営だった満映を立て直し、差別されていた中国人社員の待遇改善に努め、新たな映像機器を積極的に購入し、さらには日本から逃げるようにして満洲にやってきた左翼系映画人をも有能と判断すると躊躇することなく雇用した。私は、彼は裏金を満映に突っ込んだとばかり思っていたが、満映立て直しの資金を満洲国と関東軍から引き出しているところから、必ずしも裏金で満映を立て直したわけではないようだ。「謀略資金が満映から出ていた」という話もあるが、そもそも満映と甘粕本人とがどこまで周囲に区別されていたかは分からない。
その一方で、満映時代の甘粕は酒を飲むと荒れた。他人と飲むと、一同に童謡を歌うことを強制した。いい年した男達に口を揃えて童謡を歌わせることが、甘粕にとってどんな慰めになったのか。彼の心の奥に広がっていた荒野をのぞき込む思いがする。
本書の最後を締めくくるのは、甘粕と陸士同期で友人であった半田敏治が1944年(昭和19年)に、甘粕から聞いたという話だ。半田は「大杉一家は本当にお前が殺したのか」と聞いた。甘粕の返事は「俺はなにもやっちゃおらんよ」というものだった。
この話を半田は1967年(昭和42年)の死去直前に息子に話した。驚き、なぜ今まで話さなかったのかと尋ねる息子に、半田は「あいつが誰にも漏らすなといったからじゃ」と答えたという。
ここから浮かび上がってくるのは、巷間言われるような満洲の怪物というような姿ではない。生真面目な男がすべてを生真面目に背負い込んでしまった結果、周囲から怪物扱いされるという構図だ。男は絶望し、時に怒り、ついには自らの意志で怪物と化そうともした。敗戦時、甘粕は満映にあった金を全部配って自殺した。本書の描く敗戦後の甘粕家の窮状からするに、甘粕の握っていた裏金が敗戦国日本に流れた可能性はごく薄いだろう。
 もう一冊の『阿片王 −満洲の夜と霧−』は、かなり評価が難しい本だ。甘粕正彦と比べると無名の里見甫をテーマに据えつつ、佐野氏の粘り強い取材がどういうわけか、里見の影に見え隠れする女性関係に吸い寄せられてしまっているのである。結果、里見がどういう人物だったかは、女性絡みの間接的な描き方になってしまっている。
もう一冊の『阿片王 −満洲の夜と霧−』は、かなり評価が難しい本だ。甘粕正彦と比べると無名の里見甫をテーマに据えつつ、佐野氏の粘り強い取材がどういうわけか、里見の影に見え隠れする女性関係に吸い寄せられてしまっているのである。結果、里見がどういう人物だったかは、女性絡みの間接的な描き方になってしまっている。
里見甫は医師の息子に産まれ、長じて上海にあった東亜同文書院という学校で中国語を学んだ。東亜同文書院は、東亜同文会というアジア主義を掲げる民間団体が1901年(明治34年)に設立した学校で、主に対中貿易のための人材を育成することを目的としていた。
卒業後の里見は、青島の商社に勤務した後、1921年(大正10年)に天津の日本租界で発行されていた日本語の新聞である京津日日新聞に就職して新聞記者となる。ここで彼は中国語の語学力を磨くと共に、その語学能力を生かして中国人の間に人脈を作っていった。北京新聞、順天時報などの中国大陸で発行されていた日本語新聞に寄稿し続け、また1928年(昭和3年)には蒋介石に単独会見するなどのスクープを連発して、大物新聞記者としての実績を積み上げていった。同じく1928年に国民党と関東軍が軍時衝突を起こした済南事件では、関東軍の要請を受けて中国人人脈を生かした調停工作まで行っている。中国大陸におけるフィクサーとしての地位を確立していったわけだ。
その後、満洲鉄道勤務を経て満洲事変直後の、1931年(昭和6年)9月に、関東軍の嘱託となる。仕事は「全世界に満洲国の言い分を伝える通信社の設立」だ。この当時、日本には新聞聯合社と日本電報通信社という二つの通信社があったが、里見は──おそらく関東軍の威光を最大限に利用したのだろう──2社と協同して満蒙通信社という通信社を設立する。その内実は、新聞聯合社と日本電報通信社の満州国内の取材を中止させ、満蒙通信社の送るニュースを配信することにする、というものだった。つまり里見と彼のパトロンである関東軍は、満洲から蒙古にかけての情報流通を支配し、自らに都合の良い情報だけを流す仕組みを作り上げたのだ。
余談だが、その後日本では、1936年(昭和11年)に新聞聯合社と日本電報通信社が合併して同盟通信という単独の通信社となる。この時切り離された日本電報通信社の広告部門が、その後日本最大の広告会社へと成長していく。現在の電通である。同盟通信はといえば、敗戦後に分割されて、時事通信と共同通信となる。つまり里見は、現在の日本のニュース流通とメディア広告の基礎を作ったとも言えるだろう。
1938年(昭和13年)、関東軍の意を受けた里見は上海に移り、宏済善堂という商社を設立。上海マフィアの青幇(チンパン)に阿片を密売するようになる。阿片は販売ルートの確保が難しい。関東軍は中国人の間に広範な人脈をもつ里見に、中国人の密売組織との仲介を頼み、阿片密売で裏金を作ったわけだ。
ところで、佐野氏は敗戦後に里見の私的秘書を務めていた伊達宗嗣という人物から以下のような証言を引き出す。
「上海の宏済善堂に坂本音吉という経理係がいた。(中略)その坂本が、大東公司は阿片の重要な販路だった、と言っていた。宏済善堂から大東公司に流れる阿片で、甘粕は苦力を釣ったんだ。そして苦力を阿片づけにして、ソ満国境の防衛線を固める要塞作りに死ぬまで働かせたんだ」(同p.160)
ビンゴ!である。甘粕と阿片をつなぐものは、やっぱり苦力の口入れ屋である大東公司だったのだ。しかもその阿片は、里見の宏済善堂を経由していた。ということは、満洲国=関東軍の扱う闇の阿片は、そのほとんどが宏済善堂を経由していたのかもしれない。宏済善堂は、単に関東軍が扱う阿片を青幇に流すだけではなく、阿片の出所を分からなくするロンダリングの機能ももっていたのかも知れない。そして、その阿片流通のプロセスの中には、異能の陸軍軍人・岩畔豪雄(いわくろ・ひでお:1897〜1970。本コラム第43回参照)が設立した「陸軍のためにすべてを調達する商社」昭和通商(第27回参照)も組み込まれていたと考えるのが自然だろう。
となると古海忠之(1900〜1983)が取材にやってきた岩見隆夫に対して「アヘンは私と里見がすべて取り仕切っていたのであって、甘粕も岸さんもまったく関係ないのだ」と言ったということも、より深刻な意味を帯びてくる(第52回参照)。なぜ「私と里見」なのか。民間人として宏済善堂を実質仕切っていた里見が、満洲国高官であった古海と2人で阿片流通のすべて取り仕切っていたというなら、それは関東軍、さらには日本陸軍の阿片を通じた裏金調達の仕組みの中に、満洲国という傀儡国家が完全に組み込まれていたことを意味する。甘粕が関係ないというのは、阿片の調達の部分だろう。彼は末端の苦力への阿片の販売の部分で関与していたというわけだ。満洲国は、台湾同様の阿片専売による漸減策を採用していたから、満洲国による公的な阿片専売が、密売による裏金調達と分離しがたい表裏一体だったということだ。
さて、では敗戦から戦後にかけての里見の動きはどのようなものだったか。彼は敗戦後の1945年(昭和20年)9月6日、中華航空の旅客機で上海を出発し、福岡県の雁ノ巣飛行場に着陸、日本に帰国している。この時点で上海・福岡間の航空路が機能していたこと、そこに日本人の里見が乗れたことが大変な驚きだ。佐野氏は、里見が中華航空顧問という肩書きを持っていたので席をとることは難しくなかったと書く。彼が帰国に当たって中国人社会に張り巡らした人脈をフルに活用したであろうことが推察できる。そのまま彼は京都に偽名を使って潜伏するが、1946年(昭和21年)3月1日に、日本を占領した連合国最高司令官総司令部(GHQ)によって戦犯として逮捕され、訊問を受ける身となった。
このGHQによる訊問の中に、里見の個人財産の話も出てくる。佐野氏による要約で紹介すると、宏済善堂に蓄積された財は金の延べ棒56kgで、里見はこれを「上海の友人に預けたが後に南京政府(蒋介石率いる中華民国のこと)に没収されたと聞いている」としている。その他に、南京政府中央銀行(この南京政府がよく分からないのだが、汪兆銘の作った日本の傀儡政権のほうだろうか?)に5500万中国ドル。これはインフレが一気に進んで無価値化した、と。日本に持ち込んだのは為替手形100万円だと話す。昭和20年当時の100万円だからかなりのものだが、その後日本も一気にインフレが進み、里見が逮捕される2週間前の1946年(昭和21年)2月16日に幣原内閣は新円切り替えを発表した。
ここで里見はとんでもない証言をしている。「アヘンの金は興亜院が直接管理していたので、私はその行方について何も知らない」(同書p.251)。興亜院というのは、1938年(昭和13年)に近衛内閣によって設置された、占領地の政務と開発を行う中央官庁だ。阿片の裏金を興亜院が管理していたとなると、阿片密売は関東軍と満洲国に留まらず、大日本帝国全体の犯罪──ハーグ阿片条約違反──ということになる。
しかしGHQが、それ以上日本の阿片犯罪を追及することはなかった。追及すれば蒋介石の国民党に累が及ぶからという理由らしい。里見は1946年(昭和21年)9月に無罪放免となり、東京・成城の屋敷で暮らしはじめる。屋敷の所有名義は里見の知人で、知人が里見を世話しているかのようだ。
ここから佐野氏の興味は、戦後の里見の女性関係に向かっていってしまう。粘り強い取材の結果が開陳されるが、もう里見の財産関係の話はででこない。
──というわけで、本書の記述からは、戦後の里見は金もなくおとなしく、ただし乱脈な女性関係を展開して生きた、ということになる。が、本当にそうか。
ここで気になるのは、南京政府に没収されたという金の延べ棒56kgである。預けた上海の友人とは、ほぼ間違いなく青幇であろう。仲間と認めた者を徹底的に保護する青幇の行動原理からして、この全部を国民党に渡すとは思えない。全部を国民党に渡したふりをして、一部を残し、必ず恩ある里見に届けようとするはずだ。上海の青幇が里見に金塊ないし、金塊から換金した貨幣(おそらくドルだろう)を渡すべく行動するとしたらいつか。1949年10月の中華人民共和国成立から、12月の蒋介石の台湾への逃亡という激動が起きた時期ではなかろうか。
戦後の里見の生活からすると、決して金には困っていない。が、彼は戦後、最初の妻と離婚し、ずっと年下の2番目の妻と再婚した。その2番目の妻の産んだ子は、1965年に里見が死去した時まだ幼かった。この時、里見の友人たちが子どものためにお金を集めている。このことからして、里見の遺産は遺児の養育費にも足りなかったということが分かる。
ここに、1950年前後に里見の元に青幇から巨額な資金が届けられ、それが1955年の保守合同に流れ込むという構図を描くことが可能になる。金に恬淡とした性格だった里見は、ぽんとありったけの金を政治に渡しても全然おかしくない。
が、これは、事実とは言えない。「小説として書くなら、こういうネタもありだよ」というレベルの話である。
というわけで、次回このネタで書けるかどうかは分かりませんが、安楽椅子探偵は、もう少し続きます。しかし、図書館で読める本をクロスチェックするだけで、けっこう色々と見えてくるものだ。
【今回ご紹介した書籍】
『阿片王 −満州の夜と霧−』 (書誌データは文庫版による)
佐野眞一 著/文庫判/580頁/定価869円(税込み)/
2008年7月刊/新潮社/ISBN 978-4-10-131638-3
『甘粕正彦 −乱心の曠野−』 (書誌データは文庫版による)
佐野眞一 著/文庫判/614頁/定価859円(税込み)/
2010年11月刊/新潮社/ISBN 978-4-10-131640-6
https://www.shinchosha.co.jp/book/131640/
『佐野眞一が殺したジャーナリズム』
溝口敦・荒井香織 編著/A5判/239頁/定価1257円(税込み)/
2013年4月刊/宝島社/ISBN 978-4-8002-0764-7
https://tkj.jp/book/?cd=02076401
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2022
Shokabo-News No. 375(2022-3)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター。1962年東京都出身。現在、日経ビジネスオンラ
イン「Viwes」「テクノトレンド」などに不定期出稿中。近著に『母さん、ごめん。−50代独身男の介護奮闘記−』(集英社文庫)がある。その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数。
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は、裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月に連載しています。Webサイトにはメールマガジン配信後になるべく早い時期に掲載する予定です。是非メールマガジンにご登録ください。
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 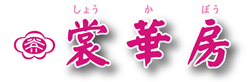
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム