第55回 阿片頼みだった満洲国の財政
『満洲国の阿片専売 −「わが満蒙の特殊権益」の研究−』(山田豪一 著、汲古書院)
前回、里見甫(1896〜1965)と甘粕正彦(1891〜1945)という2人の阿片フィクサーが、戦前・戦中の中国大陸において具体的にどのようなルートで阿片ビジネスを行っていたかを、推測を交えつつもある程度解明した。公立図書館の蔵書を読んで付き合わせるだけで、けっこう分かるものだと、私も驚いた。
 彼らの阿片ビジネスが紋様だとして、ここで問題になるのは「地」だ。つまり、そもそも20世紀の中国大陸において、阿片という作物・商品はどのような位置付けで、どのように栽培・精製され、流通していたのか。その地に乗っかるかたちで里見も甘粕も、そして関東軍も阿片に関わっていったのだから、地を押さえることで日本が彼の地で行っていた阿片ビジネスの全体像が見えてくるはずである。
彼らの阿片ビジネスが紋様だとして、ここで問題になるのは「地」だ。つまり、そもそも20世紀の中国大陸において、阿片という作物・商品はどのような位置付けで、どのように栽培・精製され、流通していたのか。その地に乗っかるかたちで里見も甘粕も、そして関東軍も阿片に関わっていったのだから、地を押さえることで日本が彼の地で行っていた阿片ビジネスの全体像が見えてくるはずである。
そこで見つけたのが、今回取り上げる『満洲国の阿片専売』だ。著者の山田豪一(1936〜2006)は、中国史の研究者。満洲国の歴史の専門家である。文字びっちりの1000ページ近い研究書で、読むのに大変苦労したが、その甲斐はあった。著者は様々な文献、特に現存する満洲国の公文書を使って、満洲国の行った阿片政策、特に植民地台湾を模倣した阿片専売政策を描き出していく。
阿片専売政策を描くことで結果的に炙り出されるのは、満洲事変で成立した満洲国のデタラメさだ。それは大日本帝国のデタラメさと言ってもいいだろう。読んでいくほどに顎が落ちるような事実が次々に明らかになっていく。
まず満洲事変直前の状況をおさらいしておこう。
日本は日露戦争の勝利で、ロシアから遼東半島先端とそこから延びる鉄道の租借権を手に入れた。もとはロシアが清朝から手に入れた権利だ。租借地は現在の旅順から大連の南半分ほど。ここを日本は関東州と呼び、関東都督府という役所を置いて治めた。1919年に関東都督府は関東軍と関東庁に分割される。関東庁は当初内閣総理大臣直轄であり、1929年に拓務省が設置されるとその下部組織となった。関東軍は陸軍の組織である。
鉄道を管理するのは南満州鉄道株式会社(満鉄)という国策会社だ。鉄道には、附属地と呼ばれる鉄道沿いの細長い土地が附属しており、この附属地の行政も関東庁が担う。当然治安を維持する警察の権利をもつのも関東庁である。
ところで、明治から昭和初期にかけての日本は、国内の貧困層を移民として海外に送り出していた。移民先は主に北米大陸と南米大陸、そして中国大陸の関東州。政府は利権が絡む関東州への移民を積極的に推進した。が、移民は「今よりも良い生活がしたい」という動機で国を出る。当時北米は経済先進地域だったが、関東州はそうではなかった。北米に行けば日本に送金できるぐらいの収入を得られたが、関東州はそうではなかった。関東州に向かった移民は、むしろ日本よりもひどい貧困に苦しむことになった。
そこで阿片がクローズアップされる。「こんなはずじゃなかったのに」と貧困に不満をもつ日本からの移民にとって、阿片の販売は確実に儲かる割の良いビジネスとなったのである。
ああ、そういうことか、だ。第26回に、第一次世界大戦において青島を占領した陸軍が阿片流通ルートを掌握して裏金を作ったという話が出てきたが、「軍を現地除隊した日本人」だけで、末端の阿片窟に至るまでの阿片の流通ができるものか不思議だったのだ。青島は関東州から見れば渤海湾を挟んだ反対側だ。もともと関東州経由で流れ込んだ日本人移民が阿片を商っていたなら、彼らと陸軍が結託しても全然おかしくはない。
ところで日本は第一次世界大戦では戦勝国側となり、戦後の国際連盟では常任理事国の地位を得た。当時アメリカは強く阿片撲滅を訴えており、原敬首相はそれに同調し、ヴェルサイユ講和条約とリンクする形でハーグ阿片条約を批准した。日本政府の組織である関東庁も阿片撲滅に動かなくてはならない。ところがそうはならなかった。というのも、関東州も台湾と同じく「徐々に時間をかけて阿片中毒患者を減らす」漸減策に基づく阿片専売制を敷いており、その収益が関東州の財政を支えていたからである。阿片は関東庁にとって必要不可欠の金づるであって、漸減策は言い訳と化していたのだ。関東庁はハーグ阿片条約の批准に庁を挙げての大反対運動を起こし、原内閣が阿片専売制の中止を打ち出した後も、漸減主義を言い訳に阿片の専売を維持し続けた。それだけでなく、関東州では日本人による阿片からのモルヒネ精製も始まった。というのも、モルヒネは阿片と違って医薬品として流通させることができたからだ。この状態が関東庁幹部の汚職として大問題になったのが関東庁阿片事件(1921)だ。
ここでまた「ああ、そういうことか」だ。第26回で、「天津では星製薬のモルヒネが最高級品として取り引きされている」という話が出てきたが、背後には阿片代替品としてモルヒネが流通するという実態があったわけだ。
そんな調子だから、関東州は阿片流通のハブとなった。流通ルートとなったのが鉄道、つまり満鉄が運営する鉄道だ。華北で栽培される阿片は満鉄に乗って華中・華南へと流れ、また大連港に集まるジャンク船がペルシャ・トルコ産の阿片を運び込み、また中国全土に散っていく。ここに、関東州が設定した関税特区制度が絡んで、大連は中国大陸への密輸の中心地となっていく。著者は、その経緯をひとつひとつ資料を渉猟して精密に追跡していく。
時に、中国の主権は清朝から孫文らが建国した中華民国に移っていく時期である。その一方で、中華民国の統治が貫徹するわけでもない。地方は軍閥が割拠する混乱状態だ。
清朝にせよ中華民国にせよ、阿片戦争以来、阿片撲滅を宿願としてきたが、満鉄経由で流通する阿片に手を出すことはできない。なぜなら満鉄周辺の附属地は関東庁警察の管轄だからだ。附属地で堂々阿片商売を営む日本人に、中国側は取り締まる権限をもっていない。
ここにさらに朝鮮人が入ってくる。当時朝鮮半島は日本の植民地であり、朝鮮人も日本国籍を持っている。彼らもまた貧困に苦しんでおり、「金になるなら」と、附属地での阿片ビジネスに参加してきたのだ。
1931年(昭和6年)、関東軍の板垣征四郎(1885〜1948)、石原莞爾(1889〜1949)らが満洲事変を起こし、傀儡国家の満洲国を建国する。計画を立案した石原の考えは、「兵器の発達から考えると、次の世界戦争が人類史最後の世界戦争となる。世界戦争の勝敗はひとえに国家の経済力で決する。だから満洲に親日の国家を立てて日本と共に高度経済成長を図り、世界戦争の勝者たるべく備える」というものだった。確かに石原には人類史的理想と巨大な構想力、そして「五族協和」と言うだけの博愛心があった。しかし彼にも、そして満洲事変に参加した軍人たちの誰にも、国家を運営するための具体的な能力はなかった。
傀儡国家を立てるためには、現地有力者の協力が必須だ。「現地の人が自らの意志で新たに国を立ち上げた」という形を取る必要があるからだ。そのための説得に当たったのが板垣征四郎だったのだが、事変が成功した後、新政府を作るプロセスは速やかに、協力した現地実力者らと軍人たち、さらには手足となって働いた日本から流れてきた“大陸浪人”たちの猟官運動の巷と化していく。その意味では、最初から満洲国は腐っていたとも言える。
ともかく速やかに満洲国に国家としての実体を与えねばならない。国家の実体とは何か? 徴税と予算執行、そしてそのプロセスとしての予算編成だ。
かくして日本から満洲国に、財政のプロが呼ばれる。そのプロこそが大蔵省から満洲にやってきた星野直樹(1892〜1978)なのである。星野の任務は、満洲国初年度の国家予算を編成することだった。
満洲国は独立国家である以上、独自通貨を発行して国内に流通させる必要がある。しかし、信用のない通貨は市場から拒否されてしまうだろう。そこで、星野が目を付けたのが阿片だった。
星野は、満洲国にも台湾と同様の阿片専売制を導入した。すると国は阿片中毒者に阿片を確実に供給する義務が発生する。専売である以上は国は阿片農家から阿片を強制的に買い上げ、かなりの量の在庫を持つ必要がある。星野はこれを満洲国初年度予算編成に利用しようとした。
専売制度で阿片を供出させる。その阿片を裏付けとして、外債を発行して日本で売りさばく。すると満洲国には大日本帝国の円が外貨として入る。この外貨を信用の裏付けとして満洲中央銀行から独自通貨を発行し、満洲国の予算を編成する──。
ここで三度「そういうことか」だ。最初っから満洲国は財政面で阿片と一体だったわけだ。第52回で取り上げた『昭和の妖怪 岸信介』(岩見隆夫著)で、満洲国高官だった古海忠之(1900〜1983)が「アヘンは私と里見がすべて取り仕切っていたのであって……」と言うわけだ。阿片ビジネスなくして、そもそも満洲国は成立しなかったのである。
星野のスキームは、すぐに分かる通り危ういものだった。そもそも阿片栽培農家がぽっと出の新しい政府にほいほいと阿片を渡すかどうか分からない。しかも、末端で誰が阿片を買い付けるのか、誰が運ぶのか、誰が責任をもって保管するのかもはっきりとしない。本書では、そのあたりの薄氷を踏むような綱渡りの状況が、一次資料を使って活写される。
その過程で、満洲国と関東庁との対立が激化する。満洲国は傀儡国家とは言え、独立国だ。だから、日本の役所である関東庁にも、日本の国策会社である満鉄にも手出しできない。もちろん阿片ビジネスが巣くう満鉄附属地にも手出しできない。そして、関東庁は自らの財政を支えている阿片の流通を、満洲国に渡す気などこれっぽっちもない。しかし、阿片が満鉄経由で関東庁に流れてしまうと、満洲国の財政が立ち行かない。
なんのことはない、表向きは「五族協和の王道楽土の独立国家」、実体は「日本人が操る傀儡国家」として、満洲国を建国してみたら、日露戦争以来の対外進出政策の出先である関東庁および満鉄と、阿片を巡る壮絶な利害関係の対立が発生してしまったのである。何やっているんだ石原莞爾? 何やっているんだ大日本帝国? である。
この対立は、その後関東軍が裏から日本政府に手を回し、1934年(昭和9年)に関東庁を解体して関東局と関東州庁に再編成するまで続く。その間、満洲国は阿片が足りないために財政的に厳しい状況に置かれ続けた。
満洲国のパトロンである関東軍は、この局面を打開すべく、1933年2月から5月にかけて熱河作戦を発動する。張学良(1901〜2001)の軍閥が支配していた熱河省に侵攻し、領土を奪ったのだ。熱河省は阿片の大産地であり、その阿片を頂こうとしたのである。「阿片がないならあるところから奪い取ればいい」──。
ところが、当然といえば当然なのだが、関東軍は「阿片の産地を切り取れば阿片が手に入る」という単純な思考しか持ち合わせていなかった。阿片ケシは6月から7月にかけての一週間程度の間に、一気に未熟な果実に傷を付けて染み出る樹液を収穫する。つまりその一週間だけ、膨大な人手を必要とする作物だ。阿片採集の労働力は、華中の中国人農家が農閑期に一気に熱河省に出稼ぎに赴くことでまかなわれていた。ちなみに出稼ぎ労働者への報酬は、樹液を乾燥させて切手のような形状に伸ばした生阿片で支払われていた。つまり出稼ぎ労働者の移動は、同時に阿片の流通ルートにもなっていたわけである。
これが、熱河省を切り取って満洲国に編入するとどういうことが起きるか。華中の出稼ぎ労働者にとって、職場である熱河省は外国ということになる。国境を越えて働きに行くには煩雑な手続きが必要になるし、場合によっては手数料を納めなくてはならない。結果、阿片採取の労働力は足りなくなり、阿片産出高は低下し……関東軍、何やってんの? なのだ。
その一方で、阿片の蔓延を憂える現地実力者たちの動きもあるし、阿片根絶を目指すアメリカを初めとした国際世論の糾弾もある。阿片に財政を頼る関東庁だけではなく、自らも阿片を加工し、莫大な利益を手に入れている台湾総督府の思惑もある。様々な思惑が絡み合うため、満洲国はなかなか石原莞爾が当初想定したように、そしてその後の関東軍が狙ったようには機能しない。
本書では、1937年(昭和12年)の日華事変勃発までの満州国を巡る阿片の状況を追っている。そこから浮かび上がってくるのは、行き当たりばったりで統一された長期のビジョンをもたない大日本帝国の姿である。阿片の生み出す利益に目が眩み、内部抗争を引き起こし、右往左往し、問題を強引に解決しようとしてさらなる問題を発生させ、結果、国際的な信用をどんどん失っていくのである。
ところで、独立国たる満洲国の統治を貫徹させるには、関東庁だけではなく満鉄を潰さなくてはならない。が、日露戦争以降の蓄積をもつ満鉄は、国策会社といいつつも、国家に近い力を蓄えており、そう簡単に関東軍や日本政府の意向でお取り潰しにすることはできない。
商工省の実力ある官僚と目されていた岸信介(1896〜1987)が、1936年(昭和11年)10月に満洲国入りしたのは、どうも満鉄の弱体化が目的であったようだ。満洲で岸は、満鉄に代わって満洲の産業を支える新たな国策会社の立ちあげに動いた。彼は、鮎川財閥総帥の鮎川義介(1880〜1967)を引き出すことに成功する。1937年(昭和12年)12月、満洲国も出資する新たな国策会社・満洲重工業開発株式会社が設立され、鮎川は社長に就任した。
鮎川は、満洲国の高度産業化は日本の力だけでは無理で、アメリカ資本を導入する必要があると考え、その方向で動いた。しかし、満洲重工設立の半年前の1937年7月、北京近郊盧溝橋の一発の銃声をきっかけに、日本軍と中国国民党軍が衝突。日華事変が発生する。当初、不拡大方針を取っていた近衛内閣はずるずると軍を増派し、紛争は拡大してやがて抜き差しならぬ状態へと泥沼化していく。状況が悪化する中、鮎川が望む満洲開発へのアメリカ資本の参加は絶望的になっていく。岸は、鮎川に梯子を掛けて満洲に進出させ、結果的に梯子をはずしたことになった。
岸は1939年(昭和14年)10月に満洲を離れて帰国。その後満洲で知遇を得た東條英機(1884〜1948)に接近し、同じく満洲で手に入れた資金(恐らくそれは、里見甫から岸へと流れた阿片密売の収益である)を使って政界に進出していくことになるのだ。
もうひとつ、陸軍が里見甫を使って阿片の密売を行ったのは、謀略の資金とする裏金を調達するためだった。では、具体的に謀略とは一体どういう行動なのか? テロか、それとも暗殺か?
もちろんテロも暗殺もあったのだが、その多くは満洲事変で板垣征四郎が行ったような、現地実力者と会談し、日本に協力するように説得することだった。 ところで中国では要人に会うためにはお土産が必要となる。具体的には現金。しかも額が大きければ大きいほど、相手を尊敬・尊重している証拠とされる。もちろん額が大きいほど、相手が説得に応じる可能性も高まる。つまり陸軍の阿片の裏金は、現地実力者と会談し、合意を取り付けるための手段だったのだ。
もちろん現地実力者はしたたかであり、口で何を言っても実際にどう動くかは別問題だ。馬占山(1885〜1950)のように、1度は満洲国建国に賛成したものの、建国後の扱いに面子を潰されて怒り、抗日ゲリラとして活動した実力者もいる。
実際問題として人間関係が複雑に絡み合う中国社会において、日本陸軍が現地実力者に渡したカネがどこにどう流れたかは分かったものではないだろう。里見甫の阿片密売で、上海マフィアの青幇に入った資金の一部が、蒋介石の国民党に流れたのと同じである。
この言葉で本稿を締めくくりたい。 何やっているんだ大日本帝国?
【今回ご紹介した書籍】
『満洲国の阿片専売 −「わが満蒙の特殊権益」の研究−』
山田豪一 著/A5判/970頁/定価16500円(税込み)/2002年12月刊/
汲古書院/ISBN 978-4-7629-2679-2
http://www.kyuko.asia/book/b10017.html
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2022
Shokabo-News No. 376(2022-4)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター。1962年東京都出身。現在、日経ビジネスオンラ
イン「Viwes」「テクノトレンド」などに不定期出稿中。近著に『母さん、ごめん。−50代独身男の介護奮闘記−』(集英社文庫)がある。その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数。
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は、裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月に連載しています。Webサイトにはメールマガジン配信後になるべく早い時期に掲載する予定です。是非メールマガジンにご登録ください。
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 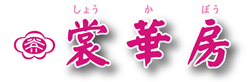
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム