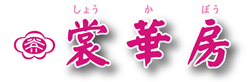 |
|
|
||||
動物の社会行動:新たな融合科学を求めて
松本忠夫・長谷川寿一
私どものジェネレーションの人間が動物の社会行動を論じるとき,まず念頭に浮かぶのは1975年に出版されたハーバード大学のウィルソン(Wilson, E.O.)による『Sociobiology 社会生物学』1)である.まるでマクラのようだと例えられたこの大きな本は,出版されるとすぐ米欧において大評判を呼んだ.とくに最終章の「ヒト:社会生物学から社会学へ」の記述をめぐって激しい「社会生物学論争」が起こった.そのいきさつはいくつかの本で書かれているが,ウィルソンの自伝『Naturalist ナチュラリスト』2)にも なまなましく書かれている.
社会生物学の核心には,ハミルトン(Hamilton, W.D.)が1964年に提唱した包括適応度と血縁選択の概念がある.これによって,動物の社会行動の説明において,それ以前のローレンツ(Lorenz,K.Z.)に代表されるウィーン学派や,アリー(Allee,W.C.),エマーソン(Emerson, A.)などのシカゴ学派,あるいは日本の今西錦司らなどが集団(種)の利益を強調していたのに対して,個体適応度また包括適応度を用いて説明すべきだとの主張,つまり「社会生物学革命」をむかえたのであった3).あのころからすでに28年たち,ハミルトンの優れた概念はすっかり市民権を得て,また,あの「氏か育ちか」を問うての激しかった社会生物学論争ももはや風化し,科学史的な興味の範疇となっているようにみえる.
ところで,日本でこの『Sociobiology』が翻訳されたのは,1975年からかなり遅れて8年後の1983年であった.米欧の動向に遅れたが,このころには日本にも蕩々となだれ込み,『Sociobiology』の和訳も出されたのである.そして訳本の出版時には,日本でも社会生物学・行動生態学は,当時の多くの研究者を引きつけブームとなっていた.そして,伊藤嘉昭,寺本 英らをリーダーとして,文部省科研費・特定研究において1983年から1987年の5年間に「生物の適応戦略と社会構造」という大型プロジェクトが行われた.
ウィルソンは社会生物学を「すべての社会行動の生物学的基礎についての体系的研究」と広い定義をしている.そして,図のように行動生物学の内部は,社会生物学,行動生態学,エソロジー,生理学的心理学,統合的神経生理学などから成り立っていて,隣接分野には集団生物学と細胞生物学があるとしている.さらに彼は,1975年から25年後の2000年の時点では,エソロジーと生理学的心理学が,一方は神経生理学および感覚生理学に,他方は社会生物学および行動生態学に蚕食されるであろうと予言した.21世紀になって3年目の現在,このウィルソンの予言は果たして当たったのだろうか?
確かにローレンツ流のエソロジーの凋落の予想は当たっていた.とくにこの学問においては「種のための社会行動」というような言い方が乱発されていたが,今ではもはやそのようなことをいう学者はごく少なくなった(いまだに亡霊は残っているが).
社会生物学・行動生態学のその後の動向はどうだろう? 確かに1980年代に入ってこの分野では爆発的に論文数が増え,いくつもの新しい雑誌が発刊された.そして,1990年代になってマイクロサテライトなど数々の遺伝的マーカー分析の手法が登場し,個体間の血縁関係の解析や集団の遺伝子組成の解析が進み,論文生産の勢いが増している.たとえば,Blackwell社から1992年に創刊された『Molecular Ecology』などをみると,この分野では著しい数の論文が毎年出されていることがわかる.一方,数理生物学による戦略モデルや量的遺伝学モデルも盛んに作られた4).しかし,2000年代に入った最近ではそれらの勢いに陰りがみられる.論文生産数は持続しているものの,ある意味では明らかに内容のマンネリ化がみられているのである.
では,新たな動向とはどのようなものであろうか? それをなるべく浮き彫りにしてみようというのが,本別冊のねらいである.結論は,本別冊の各論稿を読んで知っていただくことにするが,ウィルソンは社会生物学・行動生態学と分子生物学との融合を予言できていなかったといえるだろう.彼が大著『Sociobiology』を準備していた1970年代の初めでは,DNAのシーケンスを調べる技術はあったものの,それはたいへん手間のかかるものであり,今日のように誰でもアクセスできるDNAシーケンサーなどの便利な機器の登場などとてつもない夢だったのである.また,分子生物学の領域に大きな革命をもたらしたPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法の開発なども予想しがたいことであった.かつては行動を支配する遺伝子があることは想像されていたものの,その発現の様子を詳しく知ることは至難の業であったが,ゲノム科学の進展で,今や行動を支配する遺伝子(群)にアクセスできるようになってきたといえよう5).
今後,この融合の鍵としてソシオジェノミックス(Sociogenomics, 社会ゲノム学)があると思われる6).ほとんどの生命現象がゲノムにある情報をもととして,環境の影響も受けながら具体的に発現していることがますます明らかになっている.そのような現在において,社会行動も,それにかかわるゲノムの理解なしには本当に理解したことにはならないと思うのである.さらに,さまざまな現生生物の遺伝子・ゲノムを比較することによって,化石によらない手段でも,つまり分子系統学で生物の歴史を推察することをもきる.これも,古いイメージでいうマクロ生物学とミクロ生物学の大きな融合である.
ウィルソンが予想したエソロジーのもう一方の分極方向は,統合的神経生理学(Integrative Neurophysiology)であるが,この分野にも技術革新は押し寄せつつある.コンピューター科学やバイオ技術の進歩により脳そして神経系のメカニズムの研究が進展し(まだまだ,謎に満ちているが),そこにやはり分子生物学的な実験手法も加わり,さらにはGC・MAS(ガスクロマトグラフ質量分析)など化学物質の分析手段の向上があり,今やウィルソンの予想図式とは異なった新たな分子行動学,そして社会分子生物学の大きな台頭が始まっているように私どもには思える.
科学の歴史には,その細分化と融合化(あるいは総合化)の繰返しがあるようだ.本別冊の課題である動物の社会行動の研究分野においても,新たな融合科学が構築されていくのであろう.
文 献
1)Wilson,E.O.:社会生物学(第1-5巻).伊藤嘉昭他訳,思索社(1983-1985);合本版.新思索社(1999).
2)Wilson,E.O.:ナチュラリスト(上・下).荒木正純訳,法政大学出版局(1996).
3)佐倉 統:科学と非科学のはざまで.霊長類生態学,杉山幸丸編著,京都大学学術出版会(2000).
4)工藤慎一:行動生態学の求める答えとは?−軟派と硬派の狭間から−.遺伝,56(5),42-48(2002).
5)山元大輔:行動の分子生物学.シュプリンガー・フェアラーク東京(2000).
6)Robinson, G.E.:Sociogenomics takes flight.Science,297,204-206(2002).
(まつもと ただお・はせがわ としかず,東京大学大学院 総合文化研究科)
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.