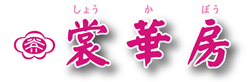 |
|
|
||||
特集II 哺乳類の冬眠
特集にあたって
近藤宣昭
われわれと同じ哺乳類の中には,人間からは想像のできない能力を備えたものがいる.冬眠はこの中でも最も不思議な生理現象の一つで,冬眠状態になると,0 ℃近い低い体温でも凍死することなく生存できる.冬眠の研究は,この現象に二つの大きなメリットを見いだすことから始まったといえるだろう.すなわち,体温低下による体のエネルギー消費の節約と,低体温に耐えて機能できる体のしくみ(低温耐性)である.
これをヒトの医療に利用しようとの試みは,50年以上に渡ってなされてきた.例えば,心臓の外科的手術の際に拍動を停止させるが,このときの酸素不足による細胞の傷害を,体温を下げてエネルギー消費を抑えることにより軽減してきた.しかし,体温の低下に伴って低温による細胞傷害や免疫機能の低下も起こり,単なる体温低下の利用には限界があることがわかってきた.この限界を取り払い,より低い体温での治療を可能にするために,冬眠動物のもつ低温耐性のしくみが重要視されてきたのである.さらに,低体温に対する耐性のほかにも,冬眠には多くの興味深い現象が観察されている.冬眠中の動物に,細菌や発ガン物質を投与したり致死量の放射線を照射しても,感染症やガン,放射線障害を起こすことなく生存できる.また,冬眠動物は想像を超えて長生きをすることも報告されている.これらの結果は,冬眠が低温に対する耐性だけではなく,多くの有害要因や因子から細胞を保護して正常な体の働きを維持するしくみであると共に,長寿や老化防止にも深くかかわる可能性を示している.このように,冬眠機構の解明は医学の発展に大きく寄与することが想像できるのである.
冬眠のしくみを明らかにするためのこれまでの試みは,冬眠に伴う細胞機能と成分の変化に視点を置いた研究と,生体に冬眠を誘導する体内因子(冬眠物質)を探索する研究に,大まかに分けることができる.しかし,細胞と生体の研究結果を相互に結びつける努力はほとんどなされてこなかったため,生体レベルで起こる冬眠のしくみを分子の動きとして捉(とら)えることはできなかった.近年になり,生体の機能を担うタンパク質や遺伝子の解析技術が急速に進歩し,冬眠研究の分野でも,分子のレベルでの理解に向けて研究が進みつつある.
このように,冬眠のしくみを理解することによって,人間社会の抱える重要問題である病気の予防や治療に新たな概念や方法を提供することが期待され,長年の間,ヒトへの応用を夢見て研究が続けられてきた.実際,上述した心臓の外科的手術(本特集 大谷の項)と共に,最近 関心が寄せられている脳傷害の抑止を目指した脳低温療法(林の項)に,低体温の意義を実感できるだろう.冬眠現象はあくまでも生体レベルの生理現象であり,細胞や分子の局部的な変化を統合し理解して,初めて利用や応用への扉を開くことができる.
本特集では,生体を統合する要である脳の重要性と,脳により制御・統合される生体システムとしての冬眠に関して最新の知見を紹介する(近藤ならびに塩見・田村の項)と共に,ヒトへの応用の前段階に位置づけられる冬眠できない動物での体温低下現象(関島の項)について概説し,最後に,実際に低体温の利用が進められている先端医療の現状と期待される冬眠応用についてまとめた.いずれも,冬眠あるいは低体温にかかわる研究で,基礎および臨床の場で活躍されている先生方に現在進行中の研究も含めて執筆していただいた.
この特集を通して,冬眠現象という特殊な生理現象の実体を理解することにより,冬眠動物でしか機能しないと思われている機構がヒトに応用できる可能性を感じていただければ幸いである.
(こんどう のりあき,三菱化学生命科学研究所 冬眠制御ユニット)
特集要約一覧
「冬眠のしくみ」近藤宣昭
ヒトへの冬眠の応用は,医学の方面で古くから関心が寄せられてきた.冬眠中の哺乳類では,0℃近い低体温への耐性が高まるだけでなく,体の抵抗性の増大や寿命の延長が観察され,医学への応用が期待されてきたからである.この期待に応えるには冬眠のしくみを理解することが不可欠であるが,冬眠の重要な特性である体温低下は,逆に,その研究にとって最大の難関になってきた.ここでは,筆者らが独自に展開してきた冬眠研究を中心にして,いくつかの新たな発見により明らかになってきた冬眠のしくみを,生体を制御する生理システムとして描く.科学的な視点からみた冬眠は,単なる体温低下現象ではない.
「脳と冬眠」田村 豊・塩見浩人
ゴールデンハムスター,ハリネズミ,コウモリ,マーモット,地リス,ヤマネなどは,冬眠行動をとる哺乳類として知られている.ゴールデンハムスターの冬眠は,体温が低下していく導入期,低体温が持続する維持期,および体温が上昇する覚醒期の3期に分類できるが,導入期および覚醒期の体温変化のタイムコースに個体差は認められない.いっぽう,維持期の持続時間は冬眠回数により変化するが,体温は必ず環境温度より1℃高い状態に保たれる.このような体温変化の特性は,冬眠時の体温変化が中枢神経系により精密に制御されていることを示している.これまでの研究により,体温を下降させる脳内物質として,アデノシン,セロトニン,オピオイドペプチド類などが見いだされており,冬眠誘発物質の候補として考えられている.また,冬眠からの覚醒時,体温を上昇させる物質として甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)が注目されている.このように,冬眠を制御すると考えられるさまざまな脳内物質が見いだされつつある.
「冬眠できない動物の体温低下現象」関島恒夫
恒温動物の中には,生息環境や食物条件の変化に応じて,体温や代謝を低下させることができるグループがいる.これらは異温動物と呼ばれ,冬眠はその代表的な生理現象である.いっぽう,異温動物の中には,1日のうちわずか数時間だけ,しかも24時間周期で休眠に入る動物たちがいる.それらの動物が示す生理現象は日内休眠と呼ばれ,休眠時の代謝量や休眠持続期間の違いから,冬眠とは明確に区別されている.日内休眠を引き起こす環境因子は,低温,食物の欠乏,日長の短縮などが知られているが,どの因子を引き金として用いるかは,それぞれの種の生活史と密接に関係している.
日内休眠や冬眠といった異温性が,恒温動物においてどのように進化してきたのかは,未だ不明のことが多く,統一的な見解をだすには至っていない.しかし,最近,恒温性を一度獲得した動物が,その生息環境条件に従い,新たに低体温機能を獲得したという説が注目されつつある.
「冬眠の応用(1):心臓手術と低体温療法」大谷 肇
心肺停止下での手術を余儀なくされる心臓および大血管の手術は,低体温法の進歩と共に発展してきた.しかし,ヒトでは人工心肺の補助なしに体温を30℃以下に下げることはできない.人工心肺装置を用いた体外循環は出血傾向,炎症反応,免疫力低下といった合併症を伴っている.これは,低体温循環停止下での手術を普及させる妨げとなってきた.冬眠動物は,冬眠期にのみ低体温に順応する機構を獲得する.冬眠の応用は,低体温循環停止下での手術を安全に行う有用な補助手段になることが期待される.
「冬眠の応用(2):脳低温療法」林 成之
重傷脳損傷の病態に対して低体温環境が優れた脳保護効果をもつことが,動物実験で確認されている.しかし,実際の重傷脳損傷患者に低体温療法を導入すると,脳保護効果よりも低体温という環境に長時間さらされること自体が患者にとって危険な状態となる.この難問を解決するために,冬眠動物が,脂質代謝への変換,中途覚醒,あるいはホルモン変化によって,循環・代謝障害の調節を行いながら自分の生命を守っている機構を参考にした,具体的な低体温管理法を紹介する.いっぽう,一定の麻酔条件下で調べられた実験動物と異なって,ヒトでは脳の直接障害に加えて生体へのストレスに伴う視床下部-下垂体-副腎系の神経内分泌ホルモンの過剰放出が発生するため,拡張型の心筋機能障害,インスリン無効の高血糖,酸素吸入無効のヘモグロビン機能障害,血液脳関門障害などが起きる.したがって,実験動物とは異なる新しい脳損傷機構に適した脳低温療法を行う必要がある.
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.