第6回 科学のためなら、どこにでも行きます
『金星を追いかけて』(ウルフ 著,角川書店)
 まずは個人的な話から。2012年5月21日に日本で見られた日食を、私は見損ねた。見る気がなかったわけではない。随分と前から数種類の日食グラスを用意して見る気満々だったのである。ところが前日夜遅くまで原稿書きにいそしんで、ちょっと仮眠をと思って横になったのが運の尽き。起きたら昼過ぎで日食は終わっていた。
まずは個人的な話から。2012年5月21日に日本で見られた日食を、私は見損ねた。見る気がなかったわけではない。随分と前から数種類の日食グラスを用意して見る気満々だったのである。ところが前日夜遅くまで原稿書きにいそしんで、ちょっと仮眠をと思って横になったのが運の尽き。起きたら昼過ぎで日食は終わっていた。
2012年は、日本で二つも太陽に関するスペクタクルな天文現象を見ることができた年だった。日食は逃してしまったが、まだもう一つがある。6月6日の金星の日面通過だ。当日、関東地方は曇りがちの天気だったが、雲間から時折のぞく太陽には、小さく、しかしくっきりと金星が入り込んでいた。じりじりと日面を移動する金星の影を、私は息を詰めて眺めた。それはあり得ないような、素晴らしい、まったくもって素晴らしい天体ショーだった。
金星の日面通過は、日食よりも稀な天体現象である。日食は場所を問わなければ、毎年2回以上、場合によっては年3回も4回も起きる。皆既食も金環食も世界全体で考えると決して稀ではない。例えば次の金環食は2013年5月9日に、オーストラリア南西部から南太平洋にかけての一帯で見ることができるし、皆既食は2015年3月20日に北海から北極海にかけての一帯で見ることができる。出かけていくのが大変なだけで、チャンスはいくらでもある。
しかし金星の日面通過はそうではない。この現象は8年間隔で2回の対で起きて、121.5年、または105.5年が空くという周期で巡ってくる。前回は8年前の2004年6月8日だったので、次は105年と半年後の2117年12月11日になる。つまり我々は、今後不死テクノロジーでも実現しないかぎり、次の金星日面通過を見ることはできない。今回、自分の住む日本で、朝ひょいっと起きたら金星の日面通過を見ることができたというのは、実はとても幸運なことだったのだ。
だから、そんな天文現象に科学的に大きな意味があるとなると、科学者達は躍起になって観測しようとする。科学的情熱に駆り立てられ、すべての困難をはね飛ばして観測に向かおうとする。
18世紀、金星の日面通過がそのような科学的観測の情熱の対象となった。今回取り上げる「金星を追いかけて」は、1761年と1769年の金星日面通過に、文字通り命を賭けた科学者達を描いたノンフィクションである。
そもそもの火種を撒いたのは、ハレー彗星を見いだした天文学者であるエドモンド・ハレー(1656〜1742)だった。1716年、彼は金星の日面通過を、地上の2点で観測することで地球と太陽の距離を測定する方法を発見した。
ここでハレーの見いだした手法をもう少し詳しく説明してみよう。というのも、本書はハレーの手法を“三角法を使って”としか解説していないのである。ここが面白いところなのに!
まず、金星の日面通過がどういう条件で起きるかを考えてみよう。当然のことながら太陽、金星、地球がこの順番に一直線に並んだ時に起きる。この順に一直線に並ぶことを天文用語では内合という。
金星の軌道面は地球の軌道面、すなわち黄道面に対して3.4度傾いている。金星は太陽を一周するごとに黄道面の北側(宇宙には上も下もないが、便宜的に“上”と思っておけば良い)にいったり南側(“下”と思っておけば良い)にいったりしているわけだ。南から北に黄道面を抜ける点を昇交点、逆に北から南に抜ける点を降交点という。金星の日面通過は、金星が、昇交点または降交点にいるときに内合になると起きるわけだ。
本稿は、メールマガジンなので図を付けることができない。というわけで、ここからは自分で図を書いて考えてもらいたい。金星の日面通過とは、地球から見て金星の影が太陽面というスクリーンに投影されることと同等だ。そして太陽、金星、地球が一直線に並んだ状態を、地球を点ではなく大きさを持った球として考えると、太陽と地球の中心を結んだ線上に金星が来ると考えることができる。日面通過とは金星が地球を追い越していくことに他ならない。つまり、地上から太陽が真上に見える緯度の場所では、金星の影は丁度太陽の直径
部分を移動していくように見える。
では、その緯度よりも北側の地点ではどう見えるかといえば、金星の影は太陽の南半球を横切っていくように見える。逆にその緯度より南側の地点からは、太陽の北半球を横切っていくように見える。つまりそこに視差が生じる。地上2点間での観測結果の視差と、2点間の距離が分かると、地球と金星の距離が分かる。三角測量と同じ原理だ。ところで、18世紀の段階で、地球と金星の太陽からの距離の比率は、公転周期を観測することでケプラーの惑星運動の法則からかなり精密に計算することができた。金星までの距離と、金星と地球の太陽までの距離の比率が分かれば、太陽と地球の距離を求めることができる。
実際には、観測を行う2点は緯度だけではなく経度もずれているだろう。そこでハレーはさらに具体的に、2地点において、金星が太陽の縁に接触して日面に潜入する時刻と、逆に日面から縁を通って出て行く時刻とを1秒単位で計測することで、視差を十分な精度で計算できることを示した。これは大変重要な指摘だった。ハレーは地上から天体現象を観測することで、遠く離れた宇宙の距離を測定できることを明らかにしたのである。
なお、この手法は金星だけではなく、水星の日面通過にも適用することができる。水星は公転周期が短いので、日面通過は金星よりもずっと頻繁に起きる。実際、水星の日面通過を使っての観測も試みられたが、当時の観測技術では十分な精度の値を得ることができなかった。水星はあまりに太陽に近すぎたのだ。 1716年の時点で、次の観測機会は1761年と1769年だった。1761年にハレーは105歳。当然そこまで生きることはできない。だから1716年の論文で、彼はくどいぐらいに観測にあたってどのような注意を払うべきかを書き込んだ。観測はなるべく沢山の地点から行うべきである。曇ってしまったら観測はできないからだ。また精度の向上のためには観測地点はなるべく世界の各地にばらけていたほうがいい。「この一つの現象をお互いに遠く離れた場所で観察してほしいと心から願う」――そう書いたハレーは1742年にこの世を去った。
しかし、18世紀という時代を考えると、ハレーの願いは法外なものであった。マゼランの艦隊が世界一周航海を成し遂げてから200年、すでに欧州各国はアフリカやアジアの各地に植民地を持ち、活発に争っていた。が、産業革命はまだ起きていない。移動に使えるのは徒歩か馬車か帆船のみで、欧州からアジアへは何ヶ月、運が悪ければ何年もかかった。長旅は危険に満ちていて、たとえ途中で命を落としたとしても文句は言えない。しかも、ハレーが求める観測を実施するためには、様々な観測機器を持って移動する必要がある。観測には多額な投資を必要とし、なおかつ命を賭けた冒険旅行となることは明らかだった。それでいて得られるものといえば、香辛料でも黄金でも、上等な毛皮でもない。金星の日面への出没を示す一組の時刻データだけである。
にも関わらずハレーの意志は、後進に引き継がれた。時代思潮も彼らに味方した。欧州は、上からの近代化を目指す啓蒙専制君主の時代に入っていたのだ。科学者を援助し、科学的事業に資金を拠出することが国の威信をライバルに示すことになり、ひいては国を富ませるという考えで、各国の君主は僻遠の地で金星日面通過を観測する遠征隊に資金を拠出した。遠征に赴く天文学者達の学問的野心には、当然ながら世俗的野心も塗り重ねられていた。地球と太陽の距離を測定したとなるとその功績は大きく、天文学者として考え得る限りの富と名声が得られるであろう。
イギリスは大西洋に浮かぶセントヘレナ島(後にナポレオン・ポナパルトの流刑地となる)とアフリカ大陸南端の喜望峰に遠征隊を派遣した。フランスはインド洋のロドリゲス島とシベリアでの観測を目指した。スウェーデンはフィンランド北方で観測を行おうとした。イギリス植民地だったアメリカからは、カナダのニューファンドランド島に天文学者が派遣された。
だが、その旅路はとんでもない苦難に満ちていた。船旅を、陸路を天候に阻まれ、欧州列強の植民地獲得を巡る争いに翻弄された。観測隊は様々な国の植民地の出先機関と敵対しつつ前進しなくてはならなかった。測定には観測地の正確な緯度経度を知る必要があるが、正確な地図があるわけではない。現地で天文観測を繰り返すことで、緯度と経度を自分で測定しなくてはならない。そして当日の天候が悪ければ、どんなに頑張っても観測はできない。このあたりの冒険譚はぜひとも本書を読んでみてもらいたい。
ありとあらゆる辛酸をなめつつ迎えた1761年6月6日、なんと観測は、あまりうまくいかなかった。遠征隊の持ち帰った時刻データを付き合わせても、十分満足できる精度で地球と太陽との距離を測定することができなかったのである。
次のチャンスは8年後の1769年、それを逃せばその次の観測機会はさらに105年後の1874年となってしまう。やらいでか――天文学者たちはますます執念を燃やして再度世界各地へ散っていった。ちなみに2回目の観測には、あの探検家ジェームズ・クック(1728〜1779)と彼の指揮する「エンデバー号」の乗組員も参加している。彼らはタヒチで観測を行った。
結論を書くなら、1769年の観測もまたあまりうまくいかなかった。日面に入り込む金星の影が、長く伸びて完全に日面に入り込む時刻、あるいは完全に出た時刻を正確に計測できなかったのだ。計測した時刻にはどのタイミングで日面に入り込んだと判断するかで、数十秒の誤差が生じてしまった。ブラックドロップ効果と呼ばれたこの現象は、当初金星に大気があるためではないかと推定されたが、現在では地球大気の乱れによるものと分かっている。
本書の旅の記録は、インドで観測を行ったフランスの天文学者ギヨーム・ル・ジャンティ(1725〜1792)の帰還で締めくくられている。「日面通過を観測した天文学者のなかで、彼は最後にヨーロッパの地を踏んだ。金星を追いかけて11年。パリに帰国すると、相続人は彼の死を宣告し、アカデミー・デ・シアンスは彼を除籍していた。」(本書p.256)
人間を人間たらしめている理由の一つが「身を滅ぼすほどの好奇心」であるということに、納得がいく一冊である。
【今回ご紹介した書籍】
『金星を追いかけて』
アンドレア・ウルフ 著/矢羽野 薫 訳
四六判/294頁/定価1870円(本体1700円+税10%)/2012年6月発行/角川書店/
ISBN978-4-04-110204-6
http://www.kadokawa.co.jp/book/bk_detail.php?pcd=201112000595
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2013
Shokabo-News No. 285(2013-2)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.日経BP社記者を経てフリーに.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『コダワリ人のおもちゃ箱』(エクスナレッジ),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.ブログ「松浦晋也のL/D」
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(偶数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 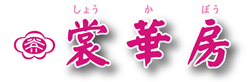
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム