第11回 電子音楽の歴史をつづる大著2冊
川崎弘二 編著『日本の電子音楽 増補改訂版』(愛育社)
田中雄二 著『電子音楽 in Japan』(アスペクト)
 安政7年3月3日(太陰暦による、グレゴリオ歴では1860年3月24日)朝、江戸城桜田門外において水戸藩を脱藩した浪士らが、登城途中の大老井伊直弼(1815〜1860)の大名駕籠を襲撃し、井伊を殺害した。桜田門外の変である。幕閣を束ねて開国政策を推し進め、反対派を弾圧した井伊が暗殺されたことにより、日本は幕末の動乱期に入っていく。
安政7年3月3日(太陰暦による、グレゴリオ歴では1860年3月24日)朝、江戸城桜田門外において水戸藩を脱藩した浪士らが、登城途中の大老井伊直弼(1815〜1860)の大名駕籠を襲撃し、井伊を殺害した。桜田門外の変である。幕閣を束ねて開国政策を推し進め、反対派を弾圧した井伊が暗殺されたことにより、日本は幕末の動乱期に入っていく。
暗殺の朝の天候は雪。 江戸は100万人以上の人口を抱える世界最大規模の都市であったが、人々の朝の所作の生活音は、降り積もった雪が吸収してしまう。無音の桜田門外に、襲撃者と警護の者の気合いと斬撃の音、やがて銀世界に広がる血だまり――襲撃はほんの数分のことだったと推定されている。この世の事とも思えぬ光景だっただろう。
今、警察庁と法務省に挟まれた桜田門交差点に立っても、襲撃の様子を思い浮かべるのは困難だ。人も風景も150余年前とは大きく変化してしまっている。が、一番違うのは環境音だろう。今の桜田門は絶え間ない自動車の騒音が響き渡っている。産業革命以前には存在しなかった音だ。
自然音しか存在しなかった時代、人間は今よりずっと静かな環境に生活していた。19世紀以降、様々な機械が生活空間に進出してきたことで、我々の“耳の風景”は大きく変化した。機械の発する騒音(noise)が否応なしに生活を浸食し始めたのだ。 noiseという単語の語源は、船酔いを意味するラテン語のnauseaなのだそうだ。それが「不快感」というより一般的な意味に変化し、やがて騒音という意味を与えられた。日本語の「騒音」がそれ専用の漢字一文字ではないあたりも考え合わせると、そもそも産業革命以前の人々には騒音という概念が存在しないか、あっても希薄だったと推察できる。
騒音が生活の中に入ってくると、音の芸術である音楽も影響を受ける。楽器を使って日常の音よりも美しい“楽音”を作り出し、楽音を組み合わせることで音楽とする――この考え方は、20世紀初頭イタリアの未来派という芸術運動でひっくり返ることになった(坂本龍一のアルバム「未来派野郎」[1986]の元ネタである)。画家であり作曲家でもあったルイージ・ルッソロ(1885〜1947)は1913年に著書『騒音芸術(L'arte dei rumori)』で、 現実に満ちる騒音こそは未来の音楽芸術へのインスピレーションの源泉であると主張。騒音を発する楽器「イントナルモーリ」を試作した。
楽音に対して騒音を対置し、音楽の中に騒音を持ち込む、あるいはもっと進んで騒音で音楽を構成するという流れは、20世紀音楽芸術の一大潮流となった。今や、CDショップには「ノイズ・ミュージック」の棚すら存在する。そこには「音楽は楽音でつくるもの」から「楽音・騒音を問わず、音により構成された創作物が音楽である」という認識の変化があるわけだ。
ところで、騒音を音楽の素材とするためには、騒音を楽音同様に自由に扱う技術的手段が必要になる。そこにはエレクトロニクスがもたらした新しい技術が二つ関係してくる。ラジオ、そしてテープレコーダーだ。
コイルとコンデンサを使って空間を伝わってくる電波を周波数別に弁別するラジオの検波回路は、エネルギーを入力すれば特定周波数を出力する共振回路にもなる。若干共振周波数がずれた二つの共振回路の出力を重ねてうなり(ビート)を発生させ、スピーカーに入力すると、人間の可聴領域の周波数の音波を発生させることができる。一番簡単な電子楽器だ。そして、フーリエ級数を使えば、原理的にはどんな音波の波形であっても周波数の異なる正弦波の和として表すことができる。かくして電子楽器は、「すべての音色を再現できる万能楽器」として期待されるようになった。この技術開発の流れは、後のシンセサイザーへとつながっていく。
一方、テープレコーダーは、録音した様々な現実の音を組み合わせて音楽を作るという流れを生みだした。テープという媒体は、ハサミで切り、粘着テープでつなぐことができたからだ。
当初この手法は“ミュジーク・コンクレート”(musique concrete:具体音音楽)と呼ばれていた。第二次世界大戦直後からフランスの技術者ピエール・シェフェール(1910〜1995)は、作曲家のピエール・アンリ(1927〜)と共同で録音した音を切り貼りすることで音楽を創作する試みを開始した。最初の作品「一人の男のための交響曲(Symphonie pour un homme seul)」は1951年に公開演奏された(公開演奏というのも妙な話だが、要は公衆の面前で録音が再生されたということ)。ただし、先駆者の常として、シェフェールはテープレコーダーではなく、レコードに録音するソノシートを使って四苦八苦しつつ作品を作っていたそうだ(すでにテープレコーダーはドイツで開発されていたが、シェフェールは使用できる環境にいなかったらしい)。
1950年代から1960年代にかけて、電子音楽にせよミュジーク・コンクレートにせよ、主に芸術音楽の分野で発展した。1960年代半ばあたりから、芸術音楽で開発された様々な手法がポピュラー音楽に流入しはじめる(例えばビートルズの「アイ・アム・ザ・ウォルラス」など)。やがて、ロバート・モーグ(1934〜2005)がモーグ・シンセサイザーを開発・販売しはじめたことで、ポピュラー音楽のエレクトロニクス化は決定的となる。1980年代に入るとデジタル音声データを自由に加工しつつ組み合わせることができるサンプラーが出現し、ラジオとテープレコーダーに起源をもつこの二つの技術は合体して今に至っている。
ここでひとつ疑問が存在する。
初期の電子音楽では、放送局が設立した電子音楽スタジオというものが、大きな役割を果たした。電子技術に精通した音楽家は稀だし、電子回路そのものも高価だった。だから、放送局が資金を拠出し、専門の技術者が常駐する電子音楽スタジオが必須だったのだ。そこで開発された技術は、放送メディアの表現力強化に役立った。
それら初期の電子音楽スタジオがどこに立地したかというと、まずドイツ・ケルンの西ドイツ放送(WDR)のケルン電子音楽スタジオ(1951年設立)、次にイタリア・ミラノのイタリア国営放送局電子音楽スタジオ(1953年設立)、そして東京のNHK電子音楽スタジオ(1953年に活動開始)……なぜかすべて第二次世界大戦枢軸国側、ありていにいえば敗戦国に立地しているのである。シェフェールで先行したはずのフランスでは、フランス国立視聴覚研究所(日本のNHK技術研究所に相当する)内に1958年になってやっと電子音楽研究組織「GRM」が設立される。 アメリカではさらに遅れて、1960年代に入ってから放送局ではなく大学に電子音楽スタジオが作られはじめたのだった。
なぜに枢軸国?
さて、やっと本題。今回紹介する『日本の電子音楽 増補改訂版』(川崎弘二編著、愛育社、2009年)と、『電子音楽 in Japan』(田中雄二著、アスペクト、2001年)は、そんな電子音楽の歴史を追った力作だ。両書とも関係者への膨大なインタビューが収録されており、それぞれ十分枕になるほどぶ厚い。が、枕に使っている閑はないだろう。とにかく面白いのだ。
『日本の電子音楽』は、主に芸術音楽の側からのアプローチに焦点をあてている。戦前の萌芽的動きから押さえた日本の電子音楽の歴史に、実際にNHK電子音楽スタジオなどで電子音楽を制作した作曲家など41人へのインタビュー、さらに著者以下5名の音楽評論家による評論を収録し、電子音楽を“美を希求する芸術のひとつ”としてとらえようとする姿勢が一貫している。
一方、『電子音楽 in Japan』は、「日本の」が「in Japan」となっていることからもわかるように、より広く「世界史の中の日本の電子音楽」、あるいは「音楽全般の中のエレクトロニクス」と大づかみにしていこうという指向が明確だ。歴史記述はバロック音楽から古典派、ロマン派と続く音楽史の記述から始まるし、芸術音楽に限らずポピュラー音楽や映画音楽にも多くの紙幅を割いている。代表的な電子音楽のCDジャケットも掲載されており、「とにかくこれ一冊で電子音楽のなんたるかをすべて網羅しよう」という意志を感じさせる。
両書を読んでいくと、技術と芸術という、一見もっとも遠く思える分野が、電子音楽では激しくぶつかりつつも協働していたことが直接的に見えてくる。芸術家は技術者がいなければ、自分なりの表現を達成できなかったし、技術者も自分の技術を必要とする芸術家を得て、初めて自分の技量が役立つということを実感できた。両者は激しく反発し合いながら、電子音楽という新しい芸術分野を形成していった。
たとえば『日本の電子音楽』収録の作曲家・江崎健次郎(1926〜)へのインタビューで、江崎はNHK電子音楽スタジオを見学に行った経験を「技師の連中も我々のことを低く見ている(笑)。機械のことなんて知らないのに、お前みたいなチンピラがやったってうまくいかない、みたいな顔つきを感じるわけです。僻みかもしれませんが(笑)。」(同書351頁)と語る。 これが、その“技師”である佐藤茂(1936〜)へのインタビューでは「(極端に正確さを求める作曲家がいたが、あまりうまくいかなかったというエピソードを語った後に)だから極端に正確さを求めないで、技師に任せたものを最終的に作曲家が構成し直すような形のほうがうまく行ったと思いますね」(同223頁)と逆照射される。「ゲージュツ的要求とかうるさく言わずに、技術者に任せろ」というわけだ。
20世紀後半の半世紀、電子音楽の世界では芸術と技術が激しく絡み合い、歴史を形作っていったのだった。
ぶ厚い両書を読み通して、先ほどの疑問「なぜに枢軸国?」に回答を与えてみよう。
まず、ヒトラーのナチス政権がリヒャルト・ワーグナー(1813〜1883)のような極端にエモーショナルな音楽を好んだことへの反動から、戦後のドイツの作曲家の間では、より理知的に音楽を構築しようという動きが生まれた。「開始何秒後に何ヘルツの音が何デシベルで鳴る」といった即物的・抽象的な表現に向かって振り子が振れたわけである。それに戦後の技術革新が重なって、まずケルンの電子音楽スタジオが成立した。
ケルンの最新動向は、毎年夏に南ドイツのダルムシュタットに作曲家たちが集まって討論するダルムシュタット夏期新音楽講習会という会合を通じて全欧州に伝わった。ところがドイツのやることに、歴史的にフランスは与しない。だから、この動きがフランスに影響を及ぼすことはなかった。代わってケルンの影響を受け、ミラノで電子音楽スタジオが開設された。
ところで1951年から1952年にかけて、フランスのパリ音楽院コンセルヴァトワールに、若き日の作曲家・黛敏郎(1929〜1997)が留学していた。黛はろくに授業に出ずに、ひたすら出歩いては主にフランスの最新動向を貪欲に吸収した(彼はシェフェールの「一人の男のための交響曲」の公開演奏会も聴いている)。帰国後、黛は同じく作曲家の諸井誠(1930〜2013)と共にNHKに働きかけ、NHK電子音楽スタジオが設立された。ただし、この時期の事情はかなり錯綜していて、NHK電子音楽スタジオも「作品を作るぞ!」と作業しては解体され、次の作品でまた集まりといった状態で、完全に常設の組織になるのは1955年以降である。
アメリカの場合は、コロンビア大学にウラジミール・ウサチェフスキー(1911〜1990)という先駆者がいて、1950年代初頭から個人的に実験と実作を繰り返していたことから、放送局ではなく大学が電子音楽研究の拠点となった。電子音楽スタジオ設立の時期的なずれは、まがりなりにも資本の論理で動く放送局と、アカデミックな大学との新技術への感度の差のせいだろう。
ところで、枕になるほどぶ厚い歴史書が2冊もあるのだから、日本の電子音楽の歴史はほぼ完璧に記述されたのかといえばさにあらず。
あの時代、東京がやることに大阪は必ず反発し、対抗していた。「AK(JOAK:東京のNHKのコールサイン)が電子音楽なるものに手を付けたそうだ」「我らBK(JOBK:NHK大阪)も電子音楽せねば」というわけで、この時期大阪でも電子音楽スタジオが立ち上がっている。
JOBKは当時大阪在住だった気鋭の作曲家・松下眞一(1922〜1990)を起用。松下はBKの支援を得て「電子音楽と声のための《黒い僧院》」(詩:北園克衛、1959年)を作曲する。この曲は欧州でも公開され好評を博したというのだが、JOBKにおける電子音楽への取り組み、その始まりから終末については両書とも記述がほとんどない。
わずかに『日本の電子音楽』で、松下がその後もBKで電子音楽制作を継続したこと、そして彼が1965年にドイツに移住したため、JOBKでの電子音楽への取り組みは終了したことが書かれているだけである。そこには当然、松下と組んだ技術者がいたはずなのに。
こういう東京偏重は、本当は好ましくないのだが……。
【今回ご紹介した書籍】
◆川崎弘二 編著 『日本の電子音楽 増補改訂版』
A5判/1116頁/定価4730円(本体4300円+税10%)/2009年3月発行/愛育社
ISBN 978-4-7500-0354-9
http://aiikusha.jimdo.com/
◆田中雄二 著 『電子音楽 in Japan』
A5判/592頁/定価3960円(本体3600円+税10%)/2001年12月発行/アスペクト
ISBN 978-4-7572-0871-1
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2014
Shokabo-News No. 295(2014-1)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」,日経トレンディネットで「“アレ”って何? 読めばわかる研究所」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『コダワリ人のおもちゃ箱』(エクスナレッジ),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.ブログ「松浦晋也のL/D」
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 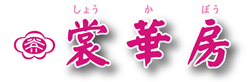
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム