第13回 テルミン、この摩訶不思議な“電気楽器”
『テルミン』(竹内正美 著,岳陽社)
 今回も電気と音楽というネタだ。隔月連載で3回続けるとそれだけで足かけ5ヶ月ということになってしまうが、これで最後にするのでご容赦願いたい。
今回も電気と音楽というネタだ。隔月連載で3回続けるとそれだけで足かけ5ヶ月ということになってしまうが、これで最後にするのでご容赦願いたい。
前々回は芸術音楽の作曲家と技術者、前回はポピュラー音楽の先駆者という視点で音楽と技術の関係を見てきたが、今回の主題は楽器製作者だ。
19世紀末、生活の中にじわじわと電気が入り込んできた時、当然楽器製作者は「電気を使う楽器を作ろう」と考えたのである。実際、楽器製作者という人種は結構革新的で、楽器の歴史をたどると、楽器製作者の発明により、音楽表現の幅が広がってきたことが分かる。ピアノは、1825年にアメリカのボイラー工場経営者アルフェーズ・バブコック (1785〜1842)が、鋳鉄フレームを発明したことで、強い張力でピアノ線を張ることができるようになり、大きなコンサートホールを満たす大音量を出せるようになった。フルートは、1847年にドイツの音楽家テオバルト・ベーム(1794〜1881)が、複数のキーが連動するベーム式フルートを発明し、正確な音程と自在に速いパッセージを演奏できるだけの運動性を手に入れた。大抵の楽器にはこれと類似した、楽器製作者の発明で音楽表現が変化したというエピソードが存在する。
史上初の「電気を使った楽器」は、1897年にアメリカの発明家サディウス・ケイヒル(1967〜1934)が発明したテルハーモニウムだ。これはなかなか壮絶な楽器で、音源はダイナモ、つまり発電機なのである。交流発電機を可聴周波数と同じ速度で回転させれば、可聴周波数の正弦波が得られる。というわけで、テルハーモニウムは145基のダイナモで正弦波を発生させ、 ピアノのような鍵盤で演奏するという楽器だった。
この時代、まだ増幅回路はない。音は大きな共鳴板を持つスピーカー(といっても原始的なイヤホンのようなものだ)から出した。このままでは、蒸気機関が発する騒音でスピーカーからの音がかき消されてしまう。そこでケイヒルは、楽器の出力をそのまま電話回線に流して、遠隔地の電話で音楽を聴くことを考えた。彼はこの構想をさらに発展させて、電話で音楽を聴かせるサービス事業を実現しようとしたが失敗した。当時の電話は、音楽が楽しめるほど音が良くなかったのだ。
ケイヒルは少々時代を先取りしすぎていた。電気を使った楽器が登場するには基礎技術が足りなかったのである。1904年に真空管が発明され、さらに1911年に現在と同じ構造のスピーカーが登場することで、初めて電気楽器の登場する下地ができ上がった。
まず、1920年にロシア人の物理学者レフ?セルゲーエヴィチ?テルミン(1896〜1993)が、電気楽器テルミンを発明。1924年にドイツのフリードリヒ・トラウトバイン(1888〜1956)が、トラウトニウムという楽器を発明。さらに、1928年になると、フランスの電気技術者モーリス・マルトノがオンド・マルトノを発明した。どれも発明者の名前にちなんだ名称だが、これは当時のメディアが「○○氏発明の新楽器」と報じたことから、本人の意志とは無関係に付いたものらしい。
これらの三つの楽器は、音を作り出す原理はみな同じである。可聴周波数だけ発振周波数をずらした2つの発振回路からの出力を重ねると、可聴周波数のうなりが発生する。これを増幅回路やフィルターを通してスピーカーに導けば、可聴周波数の音が出てくるわけだ。
それぞれの特徴がはっきり出ているのは、楽器の演奏方法だ。
トラウトニウムは、金属の薄いリボンの上に銅線を張り渡してあった。上から指で触れて、リボンと銅線が接触すると、その位置に応じた音が出る。ピアノの黒鍵と同じ位置には簡単な鍵盤があり、黒鍵の音を出すにはその鍵盤を押し込み、白鍵の音を出すには鍵盤と鍵盤の間に指を入れて、直接銅線を押し込んでリボンと接触させる。トラウトニウムには、パウル・ヒンデミット(1895〜1963)などの作曲家が曲を書いた。一番有名なのはアルフレッド・ヒッチコック(1899〜1980)が監督したサスペンス映画「鳥」(1963)の音楽だろう。「鳥」では、トラウトニウムの開発にも参加した音楽家オスカー・サラ(1910〜2002)が、鳥の鳴き声やはばたき音もトラウトニウムの演奏でつくっている。サラは、トラウトバインの死後も生涯にわたってトラウトニウムの改良を続け、またトラウトニウムを使った映画音楽を書いた。
オンド・マルトノは、ピアノと同等の72鍵の鍵盤を装備すると同時に、リボンと呼ばれる演奏機構を備えていた。右手人差し指に指輪型の電極をはめ、鍵盤手前に張り渡した金属リボンに触れると、その位置に応じた音が出る仕組みだ。リボンを使うと、深く音を揺らすビブラートや、音の高さを連続的に変化させるポルタメントといった演奏が可能になる。音の長さは左手で操作するトウッシュという操作盤のキーで指定する。トウッシュからは、音に様々な効果を付け加えることができた。
オンド・マルトノは、マルトノの一族が何十年にも渡って改良しつつ楽器を製造・販売し続けたため、電気楽器としてはトラウトニウムよりも成功した。パリ音楽院にはオンド・マルトノ科があって、今なお新たな演奏家を育てている。オンド・マルトノのために書かれた曲も多数存在し、その中にはオリヴィエ・メシアン(1908〜1992)の「トゥーランガリラ交響曲」のような20世紀を代表する名曲もある。日本人作曲家の作品では、三善晃(1933〜2013)の「オンディーヌ」、西村朗(1953〜)の「アストラル協奏曲・光の鏡」などで、オンド・マルトノを使っている。
トラウトニウムもオンド・マルトノも、従来の楽器の演奏法を踏襲しているといえるだろう。基本は鍵盤だし、オンド・マルトノのリボンは弦楽器の演奏法と類似している。が、一番早く発明されたテルミンは違った。テルミンは、奏者が何にも触れることなく演奏するのだ。本体からは2つのアンテナが突き出ていて、アンテナと人体との間の静電容量の変化で音の高さと大きさを決定しているのである。アンテナの周囲で手をひらひらと動かすと音がでてくるわけで、何も知らずにテルミンの演奏に触れた人は、魔法を見たような気分になるだろう。
発明者のレフ・テルミンという人物も、その発明品に負けず劣らず、奇妙でエキセントリックな存在だった。以下、楽器と発明者本人を区別するため、本人をレフないしレフ・テルミン、楽器をテルミンと表記する。
今回紹介する『テルミン』は、そのレフ・テルミンの生涯をまとめた伝記だ。著者は1990年代にテルミンの存在を知ってのめりこみ、ロシアに渡ってレフの親戚から直接テルミンの演奏を学んだ経歴の持ち主。実は今の日本で、テルミンはかなりメジャーな電気楽器となっているが、それは直接、間接に著者の努力の賜物でもある。その熱意は本書冒頭から明らかだ。なにしろ13世紀のレフの祖先から、話を始めるのである。
レフ・テルミンは幼少時から物理学と音楽の才能を発揮、第一次大戦に通信部隊の技術士官として従軍した後、ペトログラード工業技術大学(現サンクトペテルブルク大学)の研究員となる。そこで、気体の誘電率を測定する研究に従事する中、静電容量の変化で発振回路の周波数を変化させるというアイデアを得て、1920年にテルミンを発明した。
ロシア革命直後の、共産主義と科学万能の雰囲気が結合した熱狂の中で、テルミンは新たな芸術、あらたなプロパガンダの道具として大きな反響を引き起こした。共産党の機関紙プラウダに記事が掲載され、レフは、ウラジミール・イリイチ・レーニンと面会し、その前でテルミンを演奏するまでになった。レーニンの指示で、彼はソ連全土を回ってテルミンを演奏した。当時ソ連が進めていた全土電化計画のプロパガンダのためである。さらに彼は、従来とまったく異なる楽器テルミンで新しい共産国家ソ連を世界に印象付けるため、海外への演奏旅行に派遣された。欧州でのデモンストレーションの後、彼は1928年にアメリカに渡り、ニューヨークで音楽活動を開始した。
ニューヨークでのテルミンのデモンストレーションは成功を収め、彼は一躍社交界の寵児となった。さらに彼は、テルミンの製造販売のために、テレタッチ・コーポレーションという会社を設立する。電機メーカーのRCAが製造権を買ったために、レフは大金持ちになった。加えて彼は、ニューヨークで17歳の少女クララ・ロックモア(1911〜1998)に出会う。ヴァイオリニスト志望だったロックモアは、テルミンに魅力を感じ、レフから演奏法をマスター。後にロックモアは“テルミンの伝道師”として、テルミンの普及に力を注ぐことになる。
ソビエトから魅力的な楽器と共にやってきた大金持ち――1930年代のレフ・テルミンは、まさにニューヨークのスターだった。が、1938年、彼は突如失踪してしまう。失踪の経緯は謎が多く、本書『テルミン』でも記述はあいまいだ。実はレフは、出国にあたってソ連国家保安委員会(KGB)から諜報活動を要求されており、それに関連してKGBに拉致されたという説もある。事実だけを記述すると、彼はスターリンによる大粛正のまっただ中に帰国し、そして反革命罪で逮捕された。判決は8年の収容所送り。彼はシベリアのコリマ収容所に送られた。
幸いにして数ヶ月でシベリアからモスクワに戻され、技術者の受刑者ばかりを集めた特殊収容所で研究生活を送ることになる。この時期のソ連はスターリンが粛正をやりすぎたために、社会の人材が払底し、かといって受刑者を無罪放免にすることもできず、必要な人材をまとめて集めて「収容所内で研究所を運営する」という変な状態に陥っていたのである。彼は同じく逮捕された航空機設計者のアンドレイ・ツポレフ(1888〜1972)の下で働くことになった。この収容所で、時代の水準を突き抜けた高性能のツポレフTu-2双発爆撃機が、ツポレフやレフの手によって開発された。
やがて、コリマから引き戻されたひとりの若い技術者が、彼の助手についた。その名はセルゲイ・パヴロビッチ・コロリョフ(1906〜1966)。後にソユーズロケットを開発し、世界初の人工衛星スプートニク1号や、有人宇宙船ボストークを打ち上げたソ連宇宙開発の父である。
この調子で、レフ・テルミンの人生は最後の最後まで変転し続ける。本人としてはたまったものではなかったろうが、その様相は非常に興味深い。
彼が西側から見ると行方不明になっていた期間中、アメリカではクララ・ロックモアが、テルミンの火を絶やさず演奏活動を続けていた。やがて、第二次世界大戦後のハリウッドSF映画で、テルミンはこの世ならざる音を出す楽器として使われるようになる。特にコロリョフらが打ち上げたスプートニク1号で、西側に宇宙ブームが巻き起こると、テルミンはヒューン、ヒョーンという“宇宙の音”を出す楽器として多用されるようになり、現在に至っている。
ところで――現在日本は、単位人口当たりのテルミンの数では、おそらく世界一のテルミン普及国になっている。というのも、学研がムック『大人の科学』vol.17(2007年9月刊行)[*1]で、テルミンを取り上げたからだ。このムックでおそらく数万オーダーのテルミンが日本全国にばらまかれたはずである。もちろんムックの付録だから、ごく簡易なものだが、それでもテルミンであることには間違いない。
米ソの狭間で数奇な運命をたどったレフ・テルミン、以て瞑すべし。
【脚注】
*1 『大人の科学』Vpl.17 ふろく:テルミンmini
http://otonanokagaku.net/magazine/vol17/index.html
【今回ご紹介した書籍】
『テルミン −エーテル音楽と20世紀ロシアを生きた男−』
竹内正実 著/四六判上製/200頁/定価2200円(本体2000円+税10%)/
2000年8月発行/岳陽社/ISBN 978-4-907737-15-3
http://www.gakuyosha-p.co.jp/books/detail/hobby/theremin.html
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2014
Shokabo-News No. 299(2014-5)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」,日経トレンディネットで「“アレ”って何? 読めばわかる研究所」,日経テクノロジーで「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『飛べ!「はやぶさ」』(学習研究社),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.ブログ「松浦晋也のL/D」
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 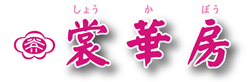
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム