第18回 原子力発電を巡る“人の世の事情”
添田孝史 著『原発と大津波 警告を葬った人々』(岩波新書)
 原子力発電を巡る問題を調べていると、どうにも技術と社会との乖離が目に付く。
原子力発電を巡る問題を調べていると、どうにも技術と社会との乖離が目に付く。
核分裂反応を実用的な発電に利用するにあたっては、4つの階層が存在したといって良いだろう。まず技術開発の階層、次に実用的なシステムを設計・建設する階層、そして原子力発電所を実際に運用する階層、最後に原子力発電を巡る社会制度の階層だ。最後の階層は行政と政治とで2つに分けてもいいかも知れない。
最初の技術開発の階層は、実にはっきりしている。物理的化学的に成立するものは成立するし、成立しないものは実現できないというだけだ。工学的に難しい課題があったとしても、時間をかけてたゆみなく研究開発を進めていけば原理的に無理というのでなければ必ず実現できる。
次の設計と建設の階層もかなりはっきりしている。出来ることは出来るし、出来ないことは出来ない。与えられた条件の中で最善を尽くすことで、その時代において可能な限り高い信頼性を実現することができる。
3番目の運用には、色々不透明なことが入り込んでくる。原発労働者を巡る多重下請けの問題や、被曝管理の問題などだ。それでも、運用の現場でいい加減なことをすると事故が起きるし、事故時の対応を間違えると死者すら出る。このレベルには原発システムというブツと真正面から向かい合っている緊張感が存在する。
ここまでは、物理的なモノの世界とダイレクトにつながっている。が、最後の原子力を巡る行政と政治は違う。正確には、モノを無視した行政も政治もあり得ないのだが、このレベルでは、上であるべきことを下と、右であるべきことを左と言いくるめて、公式文書に記載することでカッコ付きの“事実”としてしまうことが可能だ。物理的な「できる・できない」とは異なる、「人の世の事情」が優先する世界なのである。
人の世の事情は4つの階層を逆流していき、本来はきれいに「できる・できない」が区分できるはずの科学と技術の世界をも浸食していく。
原子力について調べていくと、この行政と政治の階層が、本当ならばもっと便利かつ安全に使えるはずだった原子力を、危険な代物へと変えてしまったことが見えてくる。
今回取り上げる『原発と大津波 警告を葬った人々』は、日本の行政が具体的にどのようなことをして原発の安全性を削っていったかを具体的に検証した本だ。
その基本的な構図はあっけないくらいに簡単だ。文明の存続期間は短く、自然がどのようなものかを完全に記録しているわけではない。自然科学の探究は、この地球が、この日本列島がどのような環境にあったかを完全に解明する途上にあり、日々新たな知見が蓄積されている。理解が進むほどに、日本列島は過去に大きな地震や津波に襲われていたことが分かってきた。
が、ここで人の世の事情が介入する。経済性という問題だ。安全性を確保するには金がかかる。電力会社は、発電インフラに投資し、電力を売って投資を回収し、収益を上げる。投資が小さければそれだけ回収は容易になり、収益は大きくなる。ではどうすればいいか。安全に関する規則を緩めればいい。どうやって規則を緩めるか。そのようにしても問題ないと公文書に記載するのだ。本当に問題があるかないかは、どうでもいい。そのように公文書に載っていることにこそ意味がある。人間社会では、公文書に記載されていることが行政を規定するからだ。
本書において著者は、国内9電力会社が加盟する電気事業連合会(電事連)という組織が、どのような手段を使って、あるいはこっそりと、あるいは露骨に影響力を行使し、安全性に関する基準を緩めていったかを記述していく。
電事連の動きに、監督官庁も同調していく。それどころか、著者は政府の津波対策の指針が、原発を巡る電事連の動きによって骨抜きにされた可能性すら指摘する。1997年の段階で、行政は「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべき」という方針を打ち出そうとしていた。ところがこの方針は策定の途中で消えてしまった。
東日本大震災では、津波により1万8000名あまりの方が亡くなられた。1997年の段階で「あらゆる可能性を考慮」した地震・津波対策を実施する方針が決まっていたら、その後2011年3月11日までの13年間で、一体どれほどの防災インフラが整備されていただろうか。
「でも、お金が儲かればいいじゃないか」という電力業界の態度は、原発のみならず津波被害全般を拡大したのかも知れないのだ。
いったい何故このようなことが起きたのか。ことは単に電力業界や電事連を悪者にして済む問題ではないだろう。むしろ「自分が生きている間に起きるかどうかは確率に依存する大災害より、目先の銭勘定」という、人間存在が本質的に抱える近視眼的な本能にまで遡るべきなのだろう。
これは滑稽な本能だ。マンガ家の西原理恵子は「脱税できるかな」(『できるかなV3』所載、扶桑社/角川文庫)で、税務署に踏み込まれた経験を笑いのめして描いている。大した罪悪感もなく、領収書の金額の後ろにちょろっとゼロを付け加える。ちょろっとゼロ、そしてまたゼロ。そしてある日、税務署がやってくる。構図はまったく同じだ。やってくるのは税務署ではなく津波であり、失われるのは追徴金ではなく人命であるというだけだ。
本書には、日本科学者会議編『日本列島の地震防災――阪神大震災は問いかける』(大月書店、1995年刊)からの引用の形で、1995年の阪神淡路大震災前の神戸市の地域防災計画策定の様子も掲載されている。想定震度を5にするか6にするかの議論において、市の水道関係者が「震度5か6かの議論は無駄だ」「6想定の場合の予算の程度を知らない者が勝手に6など主張するな!」と発言。それに対して市の幹部が「そうだそうだ」と喝采の声を送ったのだという。1916年の観測開始以来、兵庫県内では震度6の地震が2回起きていたにも関わらず……阪神淡路大震災では6000名を超える方が亡くなられた。
しかし、この神戸市幹部の態度を、他人事として断罪できる人は、いったいどれだけいるだろうか。
巨大地震のようないつ起きるか分からない、確率的な事象に対して、私たちはもっと賢明な態度をとるべきなのだろう。いつかは分からないが、必ず起きることなのだから、今の利益を削ってでも相応の備えをしておくべきなのだろう。ましてや、きわめて高密度のエネルギーを扱う原子力においては、ひとたび事故が起きれば、それこそ会社が倒産するぐらいの被害が出るのは自明のことだった。倒産の危機を招くぐらいなら、株主への配当を削ってでも安全対策を行うべきだったのだ。
ここで私は疑問に突き当たる。以前取り上げた『原子力発電ABC』(東京電力株式会社)を読む限り、原発導入当初の東電幹部は、原子力発電の魅力と危険性の両方を十分に承知していたふしがある。その認識は、いったいどの時点でどのような経緯で薄れ、ついには失われたのだろうか。
おそらく答えは、原発が急速に導入された1960年代から70年代にかけてのどこかに落ちているはずである。
【今回ご紹介した書籍】
『原発と大津波 警告を葬った人々』
添田孝史 著/新書判/222頁/価格(本体740円+税)/2014年11月刊行
岩波書店(岩波新書)/ISBN 978-4-00-431515-5
https://www.iwanami.co.jp/book/b226302.html
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2015
Shokabo-News No. 313(2015-7)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」,日経トレンディネットで「“アレ”って何? 読めばわかる研究所」,日経テクノロジーで「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『飛べ!「はやぶさ」』(学習研究社),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 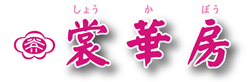
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム