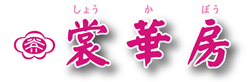 |
|
|
||||
特集 卵から親へ −新しい動物の発生のしくみ
特集にあたって
浅島 誠
(あさしま まこと,東京大学大学院 総合文化研究科)「すべての生物は卵から生ずる」と述べたのは,17世紀の生理学者であり解剖学者でもあったウイリアム・ハーヴィである.この名言は,現代の発生学を考えるうえでも,大きな礎となっている.本特集では,このハーヴィの言葉のもつ意味を改めて考えながら,各生物種speciesが歩んできた道"生き物のナチュラルヒストリー(自然史)"を分子の言葉で理解することに主眼をおいている.そして地球上にいる1000万種以上のさまざまな"生物の多様性と普遍性"を考えることも大切である.
その生物の多様性の根本である種speciesの確立に最も重要な役割を担っているのが受精である.受精は,卵と精子という二つの別々の生殖細胞の完全な融合現象であり,自然の中では同種でのみ生じる.筋肉も筋芽細胞融合でできるが,核まで完全に融合するものではない.種speciesの確立こそ,ナチュラルヒストリーの根本成立に寄与している.
なぜ,同種の卵と精子は別々の細胞であるにもかかわらず完全に融合し,1個の受精卵となりうるのか.そのステップは多段階的であり,幾つもの障壁がある.同種では,いとも簡単に二つの生殖細胞は融合するが,その種speciesと遠く離れるほど受精は成立しにくくなる.受精とはどのようなものなのか,そこに働く分子メカニズムとはどのようなものなのかについて,森澤先生らによって新しい知見をもとに受精のメカニズムを探ってもらう.
そこには,双方の生殖細胞がもつ特質がみえてくる.受精こそ生命の誕生であるともいえよう.いったい,“卵と精子が受精する”という現象はどのようなメカニズムで起こるのであろうか.卵と精子は同種の場合,お互いに相互関係をもっているといわれている.しかし,受精のメカニズムを司る実体はどのような物質であろうか.とくに精子の運動を活性化し,卵に向かって進んでいけるようにするメカニズムは大切である.また,受精時にはCa2+イオンが不可欠といわれているが, Ca2+イオンの働きは受精時にも受精後にも大きく関与している.受精時にみられる精子先体反応のしくみも,最近は遺伝子の働きを制御することによって調節することが可能になってきている.また,1個の卵には多数の精子が群がり競争が起こるが,受精は常に1対1で起こる.このような多精拒否のしくみも,受精現象ならではの大切な調節機構である.
異種間の受精の成立の難しさはなぜ起こるのかということ,受精なしの個体発生,たとえば自然単為発生や人為単為発生のしくみも興味深い.
卵から親への形づくりを分子生物学的に理解することは現代発生生物学の最重要課題である.そこには発生という時間軸にそって,つぎつぎと連続的に変化していく遺伝子発現やタンパク質の機能のような分子レベルの理解から,細胞内情報伝達,細胞間相互作用,器官形成などさまざまな複雑な過程があり,その総和として形づくりがなされている.しかも,発生プログラムの連続的調節や"個"としての統一性も必要である.
そのような複雑な過程を解き明かそうとするとき,ホメオボックス遺伝子と,TGF-β(形質転換成長因子)やFGF(繊維芽細胞成長因子)等さまざまな成長因子などのシグナル分子の存在と発見は大きな役割をもつ.
すべての生物はこのホメオボックス遺伝子とシグナル分子をもっているが,それら働きをどのように分子レベルで考えるのか.これについては最近,"ツールキット遺伝子"という新しい概念が提唱され,形づくりに共通な遺伝子としてまとめられてきている.
ツールキット遺伝子とは,どのようなものであろうか.それについては,本文でまとめられているので詳細についてはここでは省略するが,複数の遺伝子が一つのセットとして働くように考えるものである.
野地先生らは,ニワトリ・マウス・ハエ・コオロギなどさまざまな動物における形づくりや形態形成,再生現象などの研究を行なって,この分野の最先端の研究をし,素晴らしい成果をあげているが,その根底には分子で生命現象を理解しようとする姿勢がある.そのことによって,生物のさまざまな現象を分子で理解させることを可能にしつつある.
とくに今日では,ヒトを含む多くの生物でゲノムの解析と解読が急速に進んでいる.それらのゲノム解析の進展によって,各種生物が歩いてきた道と共通性および特異性がみえてきた.
ゲノムレベルでは,ヒトとチンパンジーの間にはわずか1.2 %の違いしかない.その違いがもたらすものは何であろうか.進化と遺伝子の関係も大きな課題である.
野地先生らは,上記に述べたツールキット遺伝子を例にあげながら,この進化の大問題にも迫っている.発生学と進化の問題は切っても切り離せないテーマであるが,この辺にも踏み込むことが可能となってきている.
つぎのステップとしての,幼生から親への形づくりの中でみられる変態(metamorphosis)は,まさにドラスティックな発生過程でのイベントとみることができよう.
短時間の間に今までの形とは似ても似つかぬほど大きく形を変えていく.たとえば,オタマジャクシがカエルになったり,幼虫が蛹や蝶になったりする.
ここでは主として,吉里先生らにより,オタマジャクシ幼生がカエルに変態するまでの分子機構を述べてもらう.
生物にとって,水中から陸上にあがるということは,進化のうえでも大変化である.水中では浮力もあるし,餌も豊富で,また有害な紫外線からも逃れることができる.しかし,陸上では自分の体を足で支えなければならないし,そこには1Gという重力が働く.皮膚は乾き,餌をとるのも大変である.それゆえ,カエルの個体発生では,水中から陸上にあがるときに自分自身の体を極端に小さくする.
発生における変態という現象では,体を作りかえるが,そこには細胞死や細胞吸収,新生,再構築など,生物のいろいろと複雑で面白く,かつ重要な現象が濃縮されているといえよう.そのようなメカニズムとはいったいどのようなものであろうか.
変態では,いわば体全体がいっせいに水中型から陸上型に変化しなければならない.頭部は陸上型で胴尾部は水中型というわけにはいかない.そうすると,どこか体全体を統一的にまとめあげる中枢が必要である.
一般に,変態は中枢神経系の発達とも関係している.中枢神経(脳)から出るホルモンと,そのホルモンを特異的に受け取る受容細胞または受容器官の特異性も大きなテーマである.
変態ホルモンの作用機作のメカニズムを明らかにすることは,発生のプログラムの解明でもある.変態ホルモンという特定の物質は細胞を構成する分子そのものを変化させるが,その過程ではCa2+イオンや細胞内情報伝達やシグナル分子の働きなどさまざまな物質の関与がある.
脊椎動物は水中(羊水)から陸上にあがるとき変態をし,四肢をもつようになる.四肢は脊椎動物の活動や行動,その他の機能に大きな変化をもたらす.ところで,四肢はどうしてできるのであろうか.
一般に,水中にいるとき(たとえばオタマジャクシなど),四肢は切断しても再生能力をもつが,陸上にあがるようになって成体になると,四肢を切断しても再生能力を示さなくなる.それはなぜであろうか.
また,同じ両生類でもイモリなどの有尾類は成体になっても再生能力をもつが,カエルなどの無尾類は成体になると再生能力を通常はもたない.これは,細胞や四肢の状態のどのような性質やメカニズムによるのであろうか.
また,発生途上にはもっていた再生能力は,一度失われればもう二度とその能力を復活させることはできないのであろうか.
最近,田村先生の所属する井出研究室では,この辺のメカニズムについての解明を進めて大きな成果を上げている.
失われた再生能力と,それを再び回復させる能力を獲得することとは,どのようなことであろうか.そこには,位置情報,細胞間相互作用,脱分化と再分化,細胞運動など,いろいろな生物学的に重要な問題がひそんでいることがわかる.
また,細胞の発生段階と細胞のもつポテンシャルや反応能とは,いったい分子生物学的見地からどのように理解すればよいのであろうか.細胞が解離し,再集合して構築されるとき,細胞はお互いに選別し合う.つまり,細胞のレベルにおいても他の細胞を認識し,識別・選別を行なっていることになる.
そのようにしてみると,発生過程における個々の細胞のもつ性質とはどのようなものであるかということ,また,1個の細胞の性質と細胞膜表面および細胞間物質どれほど大きな役割を担っているかということがわかる.そこに生物学的にも明らかにされなければならない問題があるが,井出先生らが開発している系はその見事なアプローチによってこれに迫っている.
動物の体の中には,さまざまな器官や組織がある.その器官のでき方の中で,消化器官のでき方について福田先生と八杉先生に述べてもらう.
われわれの体の中にある多種多様な器官(臓器)や組織は,ほとんどがもともとは胚葉間相互作用から始まって,次第に上皮−間充織の相互作用によって形成されていく.上皮−間充織の相互作用によって生ずる皮膚や腎臓,唾液腺,消化器官の形成はこの典型である.
in vitro系での器官培養という実験発生学が,現代分子生物学と結びついた見事な成果とみることができる.もともと1個の管状の構造から,やがて咽頭,胃,十二指腸,砂嚢,小腸など一連の消化器官ができあがってくる.そのでき方は,消化器官の分化過程の解明のみならず,大きくは上皮−間充織の分子メカニズムの一端を明らかにしている.
この器官培養系を用いて上皮と間充織のいろいろな組合せ実験を行い,構造と機能を調べている.とくに,胃や砂嚢や小腸分化における上皮と間充織の組合せを幾通りにも行うことによって,間充織から上皮への誘導作用と,その後の上皮からの間充織への働きかけなど,器官形成が時間という発生プログラムの要因を基本において,上皮と間充織の相互関係によって成り立っていることを示している.
そして,その相互関係を実際に司る実体としての分子を明確にしてきている.また,各消化器官の構造とそこに機能するものとして発現する遺伝子の特異性が一致する場合と,構造と機能が必ずしも一致しないものも存在することなど,その多様性を分子レベルで明らかにしている.
クローン動物の作製は現代生物学のホットな話題である.
ヒドラやプラナリアなど,切断片から個体を再生できるような再生能力の高い生物では,それぞれの切断片より1個体への復元が可能であり,再生した個体はどれもすべて同一の遺伝子をもつのでクローン生物である.
これらクローン動物の作製については,これまで哺乳類では長い間成功していなかった.ところが最近,哺乳類のクローンの技術が大きくクローズアップされてきている.
そのクローン動物の作製は核移植によって行われる.そもそも脊椎動物のクローン作りは,カエルにおける1953年のKingsとBriggsの報告に始まり,その後1963年のGurdonらによる,オタマジャクシ幼生の腸細胞から核を取り出し,それを移植することから核移植によるクローン動物の研究へと続いている.1997年のWilmutらによるクローン羊「ドリー」の作出は世界中の人に大きな影響を与えた. 今回は,哺乳動物の核移植技術のパイオニアであり,最先端の研究を行なっている角田先生らに,クローン動物のもつ意味とクローン動物がどのように発生するかについて述べてもらう.
通常の個体発生とクローン動物の発生がどのように同じであり,また違うのかについてと,その結果としての寿命はどのようになっているのかについて,豊富なデータをもとに述べてもらう.
新しい生物の技術は多大な生物学上の基礎知識をもたらすが,いっぽう,その応用については利点と欠点をもつ.それはどのようなことであるのかについて知ってもらうことも大切である.
分化した体細胞を無核の卵(核を除去した未受精卵)に移植することによって,移植された体細胞核に初期化が起こる.この分化核の初期化とはいったいどのような物質によって引き起こされ,それは具体的に染色体や核内にどのような変化が起こったことを意味するのであろうか.
この核の初期化と細胞を分化させるリプログラミング(reprogramming)がどのような現象であるかを解明することは,生物学的にもきわめて重要な問題である.
細胞周期と細胞におけるシグナル分子と反応能のタイミングの問題,テロメラーゼとの関係,核と細胞質との相互関係,寿命との関係などを調べることの意味は大きく,重要な研究テーマとなっている.
以上,今回の特集の研究を図式化して示すと,図1のような概要になる.この特集で述べられたことは卵から親への形づくりの一部であるが,多くの共通点をもっており,発生のしくみが分子の言葉で理解されつつあるといえよう.
自然科学書出版 裳華房 SHOKABO Co., Ltd.