第16回 1908年、飛行船と航空機の交錯
渡辺一英 著『日本の飛行機王 中島知久平』(光人社NF文庫)
前回(Shokabo-News 2015年1月号)は、ビジネスの才覚を兼ね備えた航空のパイオニア、エルンスト・ハインケルの自伝を紹介した。日本でも、草創期の航空に関わった全ての人が、前々回(Shokabo-News 2014年7月号)紹介した伊藤音次郎のように、純粋に飛行という夢を追ったわけではない。
ハインケルのような先覚者として、今回は一代にして巨大財閥を築いた中島知久平(1884〜1949)の伝記を紹介しよう。彼が設立した中島飛行機は、戦後の財閥解体により分割されたが、その後の合従連衡を経て、今は自動車の「スバル」ブランドで知られる富士重工業となっている。
本書は、中島の死後6年の1955年、七回忌にあわせて出版された『巨人中島知久平』(鳳文書林刊)を文庫に再録したものだ。冒頭の序文で、著者はアメリカに押しつけられた新憲法に憤り、愛国心を取り戻すためには“中島先生”のようなリーダーが必要だと書いている。つまりは中島を賛美する意図が明白で、かなり偏った本なのである。その後、中島の評伝はいくつか出版されており、彼の生涯についてバランス良く、かつ客観的に知りたければ、本書よりも『中島知久平伝 日本の飛行機王の生涯』(豊田穣著、光人社NF文庫)のほうがいいだろう。
それでも本書を取り上げるのは、同時代ならではの、中島に対する親密さと気安さが文章の随所から感じられるからだ。文章の中から、中島知久平という“怪物”が吐息もろとも立ち現れると言えばいいのか――本書からは中島のナマの生き様が感じられるのである。
著者の渡辺一英は、大正時代に「飛行界」「飛行少年」「国民飛行」といった最初期の航空出版に参加し、昭和に入ると航空時代社という当時は日本で唯一の航空専門出版社を興して一般向け航空雑誌「航空時代」を発行した、航空ジャーナリズムの先駆者だ。序文によると、渡辺が中島と知り合ったのは中島がまだ海軍に在籍していた1914年(大正3年)で、以来中島の死に至るまで交友が続いた。渡辺はかなり近いところから、常日頃の中島をウォッチしていたわけで、その意味では本書は貴重な時代の証言でもある。
1884年(明治17年)、中島知久平は群馬県新田郡尾島村(現太田市)の農家の長男として生まれた。両親から農業を継ぐと決められたために中学には進学せず、高等小学校を卒業し、そのまま家業の農業を手伝う生活に入る。このままなら知久平は、群馬の農家として一生を終えていただろう。しかし、彼は並外れて巨大な構想、それこそ妄想に近い構想を立ち上げる想像力を持っていた。
彼が高等小学校在籍中の12歳の時、日清戦争が終結し、ロシアによる三国干渉があった。ロシアがフランス、ドイツと組んで、賠償として清から得た遼東半島を返還せよと迫り、日本は従わざるを得なかった事件である。幼い知久平は、ナショナリズムをたぎらせ、憤激したが、その後が常人とは異なった。「ロシアをやっつけるためにどうしたらいいか」を必死で考え、「軍人になろう」と決意したのである。それも大日本帝国軍人として職務を全うするのではなく、「軍人になって自分を鍛え、しかる後に退役して大陸に渡り、馬賊になって力を蓄え、満州を治める頭目となり、その上でロシアと戦おう」と考えたのだった。
無茶苦茶である。が、最低限の筋は通っていて、並みの12歳が思いつくことでもない。当然家族は大反対だ。ついに知久平は反対を押し切って家出し、知人を頼って東京で勉学に励むことになった。当初は陸軍士官学校を目指していたが、父が家出を許す代わりに海軍を目指せと諭したことから、志望を変更。1903年(明治36年)、舞鶴にあった海軍機関学校に入学した。
日本海軍には軍人を養成する海軍兵学校、軍技術者を養成する海軍機関学校、そして会計や事務、兵站を担当する軍のホワイトカラーを育成する海軍経理学校という三つの学校があった。兵学校でも経理学校でもなく、機関学校に進学したことで、知久平の運命は大きく変化することになる。科学技術の世界に足を踏み入れたのだ。
彼が海軍機関学校に学ぶ間に日露戦争が勃発、日本は大国ロシアと戦って勝利した。とても勝利とは呼べないほどの薄氷の状態だったが、少なくとも国民は勝利と信じた。中島抜きで日本は勝ち、12歳の彼が立てた「軍人になって…ロシアと戦う」という構想は必要なくなった。その心の空白に入り込んだのが航空機だった。
好奇心旺盛な彼は、早い時期から欧米の雑誌を通じて空を飛ぶ新技術の飛行機についての知識を仕入れていたようだ。機関学校卒業後に乗り組んだ巡洋戦艦「生駒」が1910年(明治43年)に南米から欧州にかけての長期訪問航海に派遣され、彼はフランスにおける航空事情を自ら見聞する機会を得ることができた。
ここからは、前回取り上げたエルンスト・ハインケルと同じだ。戦力の未来は戦艦ではなく航空機にありと確信した彼は、日本独自の航空機製造に邁進する。しかし、戦艦同士の艦隊決戦が戦争の帰趨を左右すると考えられていた当時、彼の考えはなかなか理解されなかった。軍という組織に属している限りらちがあかないと考えた彼は、免官を願い出て、1917年(大正6年)に故郷に飛行機研究所を設立した。後の中島飛行機である。
会社設立の出資を得るにあたっての川西財閥の川西清兵衛(1865〜1947)との確執など、様々な紆余曲折はあった。が、軍からの注文を受けて、みるみるうちに中島飛行機は巨大化していった。「隼」「鍾馗」「疾風」といった戦闘機に、「呑龍」「飛龍」といった爆撃機など、中島飛行機で開発された傑作機は数多い。
ちなみに川西の設立した川西航空機も、「九七式飛行艇」「二式飛行艇」、そして「紫電改」戦闘機などの傑作機を生み出す会社に成長した。現在「US-2」飛行艇を生産している新明和工業である。
中島知久平は技術に明るかったが、ハインケルのように綺麗に割り切れる技術の世界に根を持つ経営者ではなかった。ひたすら民間航空の理想を追った伊藤音次郎とも異なっていた。貪欲に会社の成長を欲する、エネルギッシュな経営者だった。前々回取り上げた『空気の階段を登れ』(平木國夫著,三樹書房)には、伊藤の工場から中島が何人も職人を引き抜いて、伊藤が「なにもこんな小さな会社から引き抜かなくてもいいのに」と嘆くシーンがある。私は、おそらく著者の平木國夫が、最晩年の音次郎から直接聞いたエピソードなのではないかと想像する。
ところが、その一方で中島は伊藤音次郎とは違った意味で、理想主義者でもあった。彼の貪欲さは、理想を実現するための方法論だった。そもそも、中島飛行機設立の趣旨は、「日本の富国強兵に航空機が必要だ。誰も作らないなら自分が作る」というものだった。根っから商売人の川西清兵衛が「飛行機は儲かりそうだ」で川西航空機を設立したのとは好対照である(だから中島と川西の2人が、うまく協力してやっていけるはずもなかったわけだ)。
中島の裡には、泥にまみれる現実主義と崇高な理想とががっちりと組み合わさり、矛盾なく同居していた。本書には、そのことを示すエピソードがいくつも出てくる。
例えば、中島にとって会社は「国のため国民のため、高性能の軍用航空機を開発する」ためのものだった。だから最初から儲けることは問題外で、収益が上がるとそのすべてを技術開発と生産設備の整備につぎ込んだ――。
あるいは、会社の形態は株式会社だったが、株式は公開せず、中島の兄弟だけで保有した。「戦争の道具である飛行機の生産は、いずれ戦争が終わると失速し株価は低迷する。その時に発生する損失はすべて兄弟でかぶり社会には迷惑をかけまい」と考えたためだった――。
「本当か。中島を美化し過ぎていないか?」と思うのだが、少なくともその一部は真実だったようだ。中島飛行機に勤務した者の回想録を読むと、ことあるごとに「会社のためではなく国のため公のために働け」と訓示されたという話が出てくるのだ。回想録のひとつには、「論文を学会に提出したが、発表日が会社の仕事と重なってしまった。仕事を優先しようとしたら上司から『学会発表は公事であり、会社の仕事は私事である。私事を優先するとは何事か』と叱られた」というようなエピソードが出ていたりする。
この気風は戦後の財閥解体で、分割された会社にも受け継がれた。そんな会社のひとつ、富士精密工業が1955年になって、かつて中島飛行機に勤務していた糸川英夫・東京大学教授のロケット開発に「損得抜き」で協力していくことになるのだが――これはまた別の話である。
そして中島の内部にはもうひとつ、「妄想に近い巨大な構想を立ち上げる力」があった。彼の抱く理想とは、生まれつきの巨大な構想力/妄想力の産物だった。12歳にして満州馬賊経由でのし上がってロシアと戦おうとした構想力/妄想力が、彼を経営者というポジションに留めなかった。会社設立14年目の1930年(昭和5年)、中島は衆議院議員総選挙に立候補して当選、“政治家・中島知久平”が誕生した。理想の風呂敷を拡げていくうちに、国家のグランドデザインにまで行き着いてしまったのである。
この後、中島は中島飛行機の経営を弟の喜代一に譲り、政治に全エネルギーを投入するようになる。立憲政友会の内部を泳ぎ渡り1938年(昭和13年)には鉄道大臣として初入閣。翌1939年(昭和14年)の政友会分裂にあたっては一方の政友会確信同盟の総裁となり、戦時色が濃くなっていく中、政友会を大政翼賛会に合流させて翼賛政治の確立に一役買った。
その一方で国家経済研究所というシンクタンクを設立して、日本経済や日本社会を分析した論文も次々に発行した。これらの論文は政治家としての彼の勉強用資料だったが、同時に広く政界にも無料配布した。政治家の間で共通の時代認識を作るための道具でもあったのである。また、売名を嫌い、彼の承諾なしに『中島知久平伝』が出版されそうになった時には、印刷済みの本から著者の手元にあった原稿に至るまでを買い取って焼却したという。
対米開戦後の1942年(昭和17年)、中島の構想力/妄想力が大爆発を起こした。海軍に勤務していた時より彼は徹底した航空戦力至上主義者で、アメリカの航空産業に関する情報を継続的に入手し、分析していた。特に1939年(昭和14年)に開発が始まったB-29と、その後継機として検討されたB-36という2種類の戦略爆撃機には注目し、「いずれこれらが日本を戦略爆撃するだろう」と推察していた。戦略爆撃には戦略爆撃で対抗すべきだ。米本土を空襲し、生産設備を破壊することで対米戦を早期に講和に持ち込まねばならない。中島はそう考え、米本土を戦略爆撃するための巨大な爆撃機「Z機」構想をぶち上げた。後に「富嶽」と呼ばれることになる機体だ。
アメリカとの戦争を有利に手仕舞いするためには、これしかないと中島は考えた。富嶽こそは、彼の構想力/妄想力の生んだ理想だった。
しかし、現実が付いてこなかった。当時の日本の工業水準では、富嶽を作ることは不可能だった。開発しなくてはならない技術要素は多岐に渡り、すぐに完成させることはできなかった。また、前線で一機でも多くの戦闘機を必要としている状態で、新たに巨大な戦略爆撃機を開発するだけの国力は残っていなかった。富嶽は構想に留まり、日本は戦争に敗れた。
敗戦後、占領軍によって日本はすべての航空機の運用も研究も禁止された。中島飛行機は財閥指定を受けて解体。中島知久平はA級戦犯容疑者となった。健康上の懸念を理由に巣鴨刑務所への収監は拒み続けたが、自宅で軟禁状態に置かれた。
その状態で彼がなにをしていたかというと、本書によると、なんとジェット機と原子爆弾の勉強だったのだという。いったい敗戦後の日本でどうやって資料を手に入れたのか分からないが、とにかく中島は自分が人生を賭けた飛行機という道具に対して、まだまだ未来を見ていたのである。それも、おそらくは戦略爆撃と原子爆弾という初期冷戦の二大要素を通してだ。側近に対して「航空産業が再開する時が必ず来る」と語っていたというから、また軍用機を生産する時が来ると考えていたのだろう。
どうも、彼が長生きしていたら、その後の日本の航空産業はよほど違った経緯をたどったような気がする。政治家として活動を再開していたならば、その影響は日本の進路を変えるほどだったかも知れない。しかし、彼の命はほどなく尽きた。1949年(昭和24年)10月29日、脳出血のため自宅で死去。享年65歳。
最後に、本書から人間臭いエピソードを。中島知久平は生涯独身だったが、内縁の妻との間に息子と娘がいた。娘の結婚式に、A級戦犯容疑で軟禁中の彼は出席できなかった。当日、彼は自宅と式場をつないだ電話にかじりつきっぱなしだったそうだ。
【今回ご紹介した書籍】
『日本の飛行機王 中島知久平』
渡部一英 著/文庫版/468頁/価格(本体933円+税)
1997年4月発行/光人社(光人社NF文庫)/ISBN 978-4-7698-2158-8
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2015
Shokabo-News No. 309(2015-3)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」,日経トレンディネットで「“アレ”って何? 読めばわかる研究所」,日経テクノロジーで「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『飛べ!「はやぶさ」』(学習研究社),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(奇数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 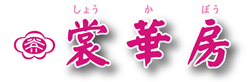
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム